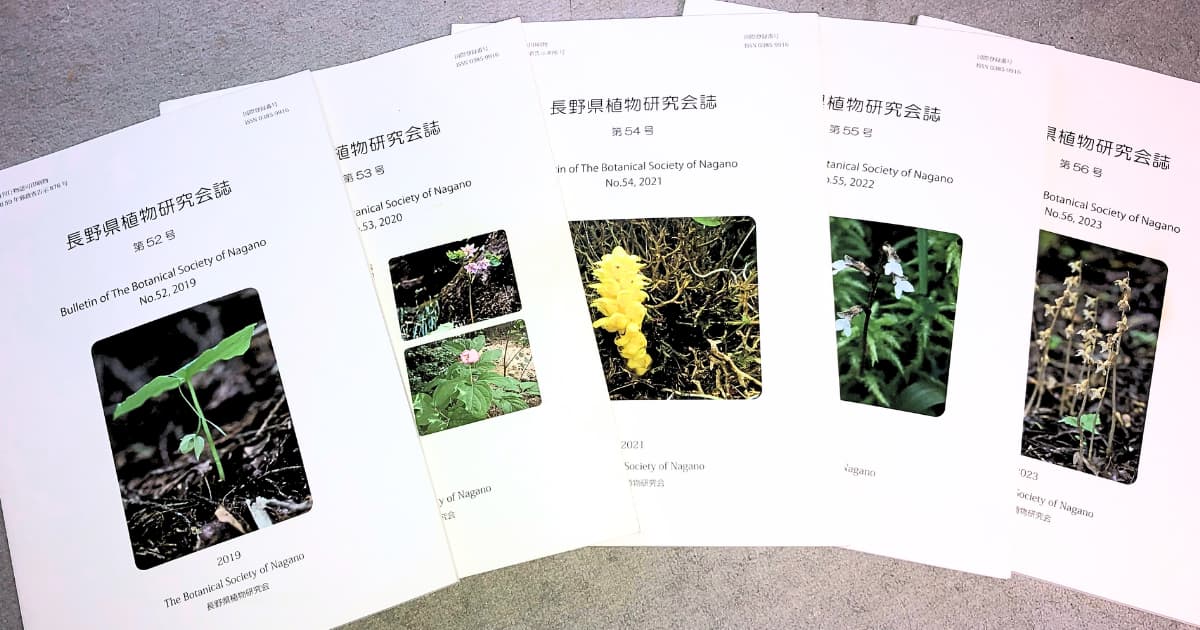長野県植物研究会誌 Bulletin of The Botanical Society of Nagano
目次
2024年 No.57
| 早川 宗志:特別寄稿 長野県産のクゲヌマランとヤビツギンラン | 1-4 |
| 藤田 淳一・井浦 和子・中村 千賀・千葉 悟志・松田 貴子:令和元年台風19 号(Hagibis) 後の千曲川氾濫原における植物相の回復状況Ⅲ | 5-19 |
| 加藤 順:日本と朝鮮半島の落葉性コナラ属の群落組成 | 21-25 |
| 齋藤 信夫:青森市月見野森林公園の森林植生 | 27-36 |
| 小山 泰弘・渡辺 隆一・望月 良男:鍋倉山巨木の谷ブナ林における33 年間の動態(1990 年~ 2023 年) | 37-40 |
| 三樹 和博:長野県ササ類地図(10)入笠山周辺のササ類相 | 41-43 |
| 飯島 敏雄:乗鞍高原の湖沼群の淡水藻類 Ⅲ 偲ぶの池 | 45-54 |
| 落合 照雄:長野県北部 無機酸性河川佐野川水域の付着珪藻類 | 55-67 |
| 齋藤 信夫:青森県深浦町十二湖におけるヤドリギ類の分布と寄主 | 69-74 |
| 小山 泰弘・柳澤 賢一・二本松 裕太:ニホンジカの個体密度が高いと林地残材による防除は出来ない | 75-78 |
| 坂口 竣弥:落葉樹林の林床に生育するヤエムグラについて | 79-84 |
| 名取 陽・伊藤 一成・五味 直喜・梅田 克己・五味 幸策:赤石山系釜無山に自生するホテイアツモリの生育状況と花の変異および保全について | 85-89 |
| 所沢 あさ子:カザグルマClematis patens C. Morren et Decne. の豊かな花色について | 91-93 |
| 大塚 孝一・松下 茂・小林 智子・野﨑 順子:長野県富士見町で生育が確認されたキクバツルデンダ(オシダ科) | 95-98 |
| 上野 勝典・上野 由貴枝:長野県で生育が確認されたクルマシダ(チャセンシダ科) | 99-99 |
| 大森 威宏・藤田 淳一:軽井沢町において確認された長野県新産国外外来種オオカナダオトギリHypericum majus (A.Gray) Britton | 101-102 |
| 小山 泰弘・尾関 雅章・玉木 一郎:新産地報告 長野県中部で見つかったフモトミズナラ | 103-105 |
| 竹重 聡:富士見町釜無川上流域で確認されたハナハギ | 107-108 |
| 藤田 淳一:長野県植物誌改訂調査で確認された県新産種の紹介VI | 109-117 |
| 大塚 孝一:長野県北信地域の植物相研究 | 119-134 |
| 藤田 淳一・星山 耕一・松田 貴子・中村 千賀・大塚 孝一・川上 美保子・石田 祐子:長野県植物誌パイロット版IV | 135-144 |
| 中村 千賀:長野県植物誌改訂 研究史資料12:高橋秀男 | 145-157 |
| 横内 文人:故・小泉秀雄先生の野帳(19) | 159-170 |
| 尾関 雅章・大塚 孝一・星山 耕一・藤田 淳一・石田 祐子:「長野県植物目録」補遺(2) | 171-178 |
| 植物ニュースno.203-218. | 179-184 |
| 新刊紹介 | 185-185 |
| 追悼:林一六先生 (土田 勝義・佐藤 利幸) | 187-189 |
| 追悼:松田行雄先生 (横内 文人・土田 勝義) | 191-193 |
| 2023 年度長野県植物研究会活動報告 (大塚 孝一) | 195-195 |
| 長野県植物研究会2023 年大会及び第225 ~ 227 回例会報告 (藤田 淳一・千葉 悟志) | 197-205 |
| 長野県植物研究会誌第56 号(2023)寄贈先 | 207-208 |
| 会員名簿2024 | 209-230 |
2023年 No.56
| 山ノ内 崇志: (特別寄稿)長野県新産のヒルムシロ属の雑種オオササエビモPotamogeton ×anguillanus Koidz. | 1-2 |
| 土田 勝義: 美ヶ原高原王ヶ頭におけるシナノザサ群落の刈取りによる草原再生 | 3-12 |
| 齋藤 信夫: 青森県平川市白岩森林公園の森林植生 | 13-22 |
| 三樹 和博: 長野県ササ類地図(9)上信国境のササ類相 | 23-25 |
| 所沢 あさ子: リョウノウアザミ(キク科アザミ属)(Cirsium grandirosuliferum Kadota)の群生地は生物多様性の宝庫 シロバナリョウノウアザミの発見から | 27-32 |
| 飯島 敏雄: 乗鞍高原の湖沼群の淡水藻類 Ⅱ まいめの池 | 33-40 |
| 落合 照雄: 無機酸性御射鹿池の水生微生物相 茅野市 | 41-46 |
| 加藤 順: ブナ林とミズナラ林の群落組成の量的分析 | 47-51 |
| 小山 泰弘・柳澤 賢一・二本松 裕太: 林地残材はニホンジカの食害低減に貢献できるのか | 53-57 |
| 齋藤 信夫: 青森県内におけるニッコウキスゲの花柄数と果実数の経年変化 | 59-66 |
| 坂口 竣弥: オオバノヤエムグラの成長に伴う葉の形態変化とビンゴムグラとの関係について | 67-72 |
| 井浦 和子: 早咲きのママコナ属Melampyrumの観察 その2-ハヤザキママコナ(仮称)は何者?- | 73-78 |
| 大塚 孝一: 長野県のフジノキシノブとクロノキシノブ | 79-81 |
| 上野 勝典・上野 由貴枝: 南木曽町田立で見つかったヌカイタチシダモドキと周辺の暖地性シダ | 83-87 |
| 井浦 和子: 長野県新産キイムヨウランLecanorchis hokurikuensis Masam. f. kiiensis (Murata) Seriz.の報告 | 89-91 |
| 井波 明宏・設樂 拓人・川田 清和・清野 達之・上條 隆志:長野県南佐久郡川上村におけるアオキランの新産地報告 | 93-94 |
| 野口 健: 東御市の山間地に群生するマルミノウルシ | 95-101 |
| 竹重 聡・五味 直喜・木下 義彦・佐藤 仁昭・宮澤 豊・尾関 雅章・ 菅原 敬:富士見町釜無川流域で確認されたツルガシワ(キョウチクトウ科) | 103-106 |
| 所沢 あさ子: 新産地報告 | 107-110 |
| 藤田 淳一: 長野県植物誌改訂調査で確認された県新産種の紹介V | 111-118 |
| 大塚 孝一: 長野県佐久地域の植物相研究 | 119-138 |
| 千葉 悟志・藤田 淳一・吉沢 敏江・有川 美保子・丸山 優子:長野県植物誌改訂に向けた大北地域の取り組みと標本保管の意義について | 139-144 |
| 松田 貴子: 安曇野地区における長野県植物誌改訂に向けた活動報告 | 145-147 |
| 藤田 淳一・大塚 孝一・川上 美保子・星山 耕一・松田 貴子・中村 千賀・上野 勝典・石田 祐子:長野県植物誌パイロット版Ⅲ | 149-160 |
| 大塚孝一: 長野県植物誌改訂 文献資料6:「植物分類,地理」に掲載された植物相・植生等に関する文献目録 | 161-162 |
| 中村千賀: 長野県植物誌改訂 研究史資料9:浅野 一 男 | 163-168 |
| 中村千賀: 長野県植物誌改訂 研究史資料10:水島 正美 | 169-175 |
| 大塚孝一: 長野県植物誌改訂 研究史資料11:金井弘夫 | 177-183 |
| 横内文人: 故・小泉秀雄先生の野帳(18) | 185-196 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(18) | 197-198 |
| 植物ニュース(195-202): 195キヨスミヒメワラビ(大塚孝一),196イワガネゼンマイのN型・S型(大塚),197ウスヒメワラビ(上野勝典・上野由貴枝),198シロテンマ(上野・上野),199ナガオノキシノブ(大塚),200キミノウラジロノキ(大塚),201モモイロラショウモンカズラ(大塚),202フモトミズナラ(大塚) | 199-201 |
| 井浦 和子:コラム 長野県植物研究会誌 投稿原稿のひな形例 | 203-206 |
| 2022年度長野県植物研究会活動報告 (大塚 孝一) | 207-207 |
| 長野県植物研究会2022年大会及び第224回例会報告 (藤田 淳一・千葉 悟志) | 209-217 |
| 長野県植物研究会誌第55号(2022)寄贈先 | 219-220 |
| 会員名簿2023 | 221-222 |
2022年 No.55
| 野口健・川上美保子・岩佐富美子・小山田八重子・中島洋子・蛭間 啓:長野県植物誌改訂にかかる上田地区の調査状況(2018-2020) | 1-12 |
| 齋藤信夫: 青森県青森市の高森山における森林植生 | 13-21 |
| 竹重 聡・戸谷 弥生: 長野市小鍋の風穴石室における植物フロラ | 23-26 |
| 藤田 淳一・井浦 和子・中村 千賀・千葉 悟志・松田 貴子:令和元年台風19号(Hagibis)後の千曲川氾濫原における植物相の回復状況Ⅱ | 27-42 |
| 三樹 和博: 長野県ササ類地図(8)長野県北西部のササ類相 | 43-44 |
| 飯島 敏雄・永沼 治: 松平の池(池の平の池)の珪藻類 | 45-49 |
| 落合 照雄: 北海道の淡水域の付着藻植生 洞爺湖、フキダシ湧水そして釧路湿原温根内の付着藻相 | 51-64 |
| 土田 勝義: 松本市周辺の身近な絶滅危惧植物のゆくえ(1) | 65-67 |
| 小山 泰弘・柳澤 賢一・鈴木 智之・新其 楽図・西村 尚之:北八ヶ岳亜高山帯針葉樹林におけるニホンジカの行動と樹木被害との関連性 | 69-76 |
| 加藤 順: 菅平アカマツ林の葉面積指数の推測 | 77-79 |
| 齋藤 信夫: 津軽地方におけるヤドリギ類の分布 | 81-87 |
| 井浦 和子: 早咲きのママコナ属Melampyrumの観察 | 89-92 |
| 尾関 雅章・竹重 聡: ミヤマエンレイソウ Trillium tschonoskii Maxim. の花色変化 | 93-95 |
| 所沢 あさ子: 新産地・推定雑種・新品種報告 ・タチキランソウ(Ajuga makinoi Nakai)・ニシキゴロモ(Ajuga yesoensis Maxim. ex Franch. et Sav. var. yesoensis)・ツクバキンモンソウ(Ajuga yesoensis Maxim.ex Franch. et Sav. var. sukubana Nakai) の3種の分布が重なる飯田市山本のハナノキ湿地周辺 | 97-100 |
| 大塚 孝一・小林 智子・小山 京子・若宮 稔美・松下 茂・野崎 順子・佐藤 利幸:長野県富士見町で生育が確認されたメヤブソテツ(オシダ科) | 101-102 |
| 井浦 和子・藤田 淳一: 長野県高山村におけるフモトミズナラの確認 | 103-105 |
| 横内 文人・横内 怜子: 松本市内のホウライシダの分布 | 107-108 |
| 所沢 あさ子: 新産地報告 ヤクシマヒメアリドオシラン『飯田市山本西山の湧水湿地群はヤクシマヒメアリドオシランの楽園』 | 109-113 |
| 所沢 あさ子: 新産地報告 | 115-117 |
| 上野 勝典・上野 由貴枝: 新産地報告 (14) | 119-120 |
| 上野 勝典・上野 由貴枝: 長野県産シダ植物の新産地 (12) | 121-123 |
| 栁澤 衿哉: 長野県新産外来種の報告 | 125-131 |
| 藤田 淳一: 長野県植物誌改訂調査で確認された県新産種の紹介IV | 133-142 |
| 藤田 淳一・松田 貴子・大塚 孝一: 奥原弘人氏コレクション調査報告 | 143-154 |
| 石田 祐子: 神奈川県立生命の星・地球博物館(KPM)収蔵標本および画像資料から見出された『長野県植物目録 (2017年版)』に追加すべき種 | 155-158 |
| 藤田 淳一・大塚 孝一・星山 耕一・上野 勝典・上野 由貴枝・松田 貴子・中村 千賀・石田 祐子・島野 光司: 長野県植物誌パイロット版Ⅱ | 159-166 |
| 大塚 孝一: 長野県産種子植物のタイプ標本 (3) 被子植物(双子葉植物)タデ科~セリ科 | 167-181 |
| 大塚 孝一: 長野県植物誌改訂 文献資料5:「植物研究雑誌」に掲載された植物相・植生等 | 183-188 |
| 中村 千賀: 長野県植物誌改訂 研究史資料7:古瀬 義 | 189-193 |
| 中村 千賀: 長野県植物誌改訂 研究史資料8:浜 栄助 | 195-199 |
| 横内 文人: 故・小泉秀雄先生の野帳(17) | 201-212 |
| 植物ニュース(184-194): 184タイミンガサ(大塚孝一),185ノキシノブ(大塚),186コゲジゲジシダ(大塚),187シロバナオトメエンゴサク(大塚),188ヤマナシテンナンショウ(星山耕一),189シロバナコシジタビラコ(新称)(藤田淳一),190チシマオドリコソウ(上野勝典・上野由貴枝),191キタノミヤマシダ(上野・上野),192オクヤマシダ(大塚),193ミョウギシダ(大塚),194シモツケヌリトラノオ(大塚) | 213-216 |
| 新刊紹介 | 217-218 |
| 2021年度長野県植物研究会活動報告 (大塚 孝一) | 219-219 |
| 2021年小例会(試行)の報告 (藤田 淳一) | 221-221 |
| 交換雑誌・寄贈雑誌など | 231-234 |
| 会員名簿2022 | 235-236 |
2021年 No.54
| 藤田淳一・井浦和子・中村千賀・千葉悟志・松田貴子:令和元年台風19号(Hagibis)後の千曲川氾濫における植物相の回復状況 | 1-20 |
| 千葉悟志・藤田淳一・吉沢敏江・有川美保子・丸山優子:長野県大町市におけるスキー場駐車場に見る湿地の植物相について | 21-23 |
| 川上美保子・大塚孝一:長野県上田小県地域の植物相研究 | 25-36 |
| 齋藤信夫:青森市田頭山の森林植生 | 37-46 |
| 小山泰弘・鈴木智之・西村尚之:ニホンジカの出没状況からみた北八ヶ岳における亜高山帯針葉樹林への影響 | 47-53 |
| 堤 久:松川町の天竜川河原に生育するアスター属の植物相(2) | 55-57 |
| 小山泰弘:松本市の住宅地周辺にある社叢の評価 | 59-64 |
| 三樹和博:長野県ササ類地図(7)長野市に分布するササ類 | 65-68 |
| 齋藤信夫:青森県の津軽十二湖におけるイイギリの生育立地と分布 | 69-76 |
| 飯島敏雄:乗鞍高原の湖沼群の淡水藻類 Ⅰ牛留池 | 77-84 |
| 落合照雄:鹿児島県屋久島の付着淡水藻類相 | 85-95 |
| 大塚孝一:長尾県におけるベニシダの分布Ⅲ−西暦2000年から20年後の分布変化 | 97-99 |
| 坂口竣弥:長野県におけるキクムグラの2タイプの比較とビンゴムグラとの関連性について | 101-106 |
| 松田行雄・浅田太郎:霧ヶ峰八島ヶ原湿原の湿原群落の泥炭水位と水質(pH) | 107-120 |
| 加藤 順:オニグルミのパイプモデル理論の適用 | 121-122 |
| 土田勝義・坪井勇人・伊藤英喜:白馬五竜高山植物園20年の歩み一観光的な植物園から公的価値の高い植物園へ | 123-133 |
| 竹重 聡・根橋信水・牛丸工・鈴木安裕・東城幸治:北アルプス上高地の複数の自生で確認されたカミコウチヤナギ(ケショウヤナギ×オオバヤナギ)の形状特性 | 135-141 |
| 竹重 聡・五味直喜・木下義彦・佐藤仁昭・宮澤豊・酒井志摩・菅原敬: 南アルプス鋸岳で初めて発見されたオニク(ハマウツボ科)の新品種キバナオニク | 143-146 |
| 井浦和子・藤田淳一:長野県北部におけるフモトミズナラQuercus crispula Blume var. mongolicoides (H.Ohba) Seriz.とみられる木本の生育確認 | 147-148 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(13) | 149-152 |
| 藤田淳一:長野県植物誌改訂調査で確認された県新産種の紹介Ⅲ | 153-162 |
| 宮崎弘規:安曇野河川敷のウチワサボテン(第223回例会報告を読んで) | 163-164 |
| 藤田淳一尾関雅章・星山耕一:長野県植物誌パイロット版 | 165-169 |
| 大塚孝一:長野県産種子植物のタイプ標本(2)被子植物(双子葉植物)ケシ科〜アブラナ科 | 171-182 |
| 大塚孝一:長野県植物誌改訂 文献資料4:「信州大学教育学部附属志賀自然教育研究施設」に 掲載された植物相・植生等に関する文献目録 | 183-185 |
| 中村千賀:長野県植物誌改訂 研究史資料5:井上 健 | 187-194 |
| 中村千賀・新井勝利:長野県植物誌改訂 研究史資料6:佐藤邦雄 | 195-200 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(16) | 201-212 |
| 大塚孝一:2020年度大会・例会等研究会活動報告 | 213 |
2020年 No.53
| 土田勝義:霧ヶ峰高原におけるササ刈取りによる草原景観の再生 | 1-13 |
| 藤田淳一・大塚孝一:長野県栄村における国道沿い切土斜面湿地の植物相と植生 | 15-20 |
| 三樹和博:長野県ササ類地図(6)諏訪地域北西部のササ類相 | 21-23 |
| 齋藤信夫:青森県津軽地方におけるイイギリ混交林の種組成と生育地の特徴 | 25-33 |
| 齋藤信夫:青森市とその周辺におけるヤドリギ類の分布 | 35-41 |
| 加藤 順・林一六:長野県菅平におけるアカマツ林38年間の樹齢組成の変化 | 43-45 |
| 加藤 順・林一六:樹木の地上部現存量を求める相対成長式 | 47-49 |
| 飯島敏雄:木曽駒ヶ岳、剣ヶ池の珪藻類 | 51-57 |
| 落合照雄:数種の綺麗な水域の付着珪藻類−柿田川、三島花藻の里、お種池そして小聖水源の付着珪藻 | 59-67 |
| 堤 久:松川町の天竜川河原に生育するアスター属の植物相(1) | 69-74 |
| 小山泰弘・鈴木智之・西村尚之:北八ヶ岳の亜高山帯針葉樹林における森林の攪乱履歴がニホンジカの行動に及ぼす影響(速報) | 75-80 |
| 尾関雅章・大塚孝一・井田秀行:栄村野々海におけるヒメカイウCalla palustris L.の生育状況:UAVによる開花株の観測 | 81-83 |
| 中村千賀:長野市内のチャンチン(センダン科)の生育とその利用について | 85-88 |
| 上野勝典・上野由貴枝・高橋順子:トヨボタニソバの新産地 | 89-90 |
| 高橋 勸:飯山市近郷の植物〜長野県植物誌改定に寄せて〜 | 91-92 |
| 藤田淳一:長野県植物誌改訂調査で確認された県新産種の紹介Ⅱ | 93-99 |
| 大塚孝一:長野県産種子植物のタイプ標本(1)裸子植物・被子植物(単子葉植物) | 101-110 |
| 大塚孝一:長野県植物誌改訂 文献資料3:「信州大学環境科学年報」に掲載された植物相・植生等に関する文献目録 | 111-113 |
| 中村千賀:長野県植物誌改訂 研究史資料3:丸山利雄 | 115-119 |
| 中村千賀:長野県植物誌改訂 研究史資料4:高橋 勸 | 121-124 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(15) | 125-136 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(17) | 137-138 |
| 藤田淳一・千葉悟志:長野県植物研究会2019年度大会及び221例会の報告 | 139-149 |
| 藤田淳一・千葉悟志:長野県植物研究会第222〜223回例会報告 | 151-158 |
2019年 No.52
| 加藤 順:構成する属からみた常緑性と落葉性のコナラ属の群落組成の比較 | 1-8 |
| 三樹和博:長野県ササ類地図(5)八ヶ岳周辺のササ類相(追捕) | 9-11 |
| 尾関雅章:逆谷地湿原における野生動物による湿原植生の攪乱:UAVによる簡易観測 | 13-15 |
| 中村千賀・林部直樹・田辺智隆・戸隠奥社の杜と杉並木を守る会: 戸隠神社奥社社叢林における巨樹調査の記録 | 17-22 |
| 小山泰弘・林部直樹:戸隠奥者杉並木における近年の樹高成長 | 23-31 |
| 金子裕美・加藤順:オニグルミ(Juglans mandshurica var. sachalinensis)の分布拡大の推測 ニホンリス(Sciurus lis)が貯蓄して発芽したオニグルミ稚樹の樹高構成 | 33-37 |
| 加藤 順:長野県佐久市平尾山山麓におけるアカマツの年輪解析 | 39-41 |
| 齋藤信夫:青森県の折腰内に生育するカラスザンショウのDBHと樹幹傾斜度及び樹齢について | 43-48 |
| 齋藤信夫:梵珠山の登山道沿い周辺におけるヤドリギの宿主について−分布高度・直径・分布− | 49-53 |
| 飯島敏雄:富士見町入笠湿原の珪藻類について | 55-61 |
| 落合照雄:層雲峡の渓流、阿寒湖そして別府弁天池の付着珪藻類 | 63-71 |
| 松井雅之:長野県で発見・記載された2種及び未記載3種 | 73-76 |
| 川上美保子・野口健・星山耕一:ミクニテンナンショウを上田市で再確認 | 77-78 |
| 星山耕一:長野県新産帰化植物花ハマセンブリCentaurium tenuiflorum (Hoffmanns. et Link) Fritschの報告 | 79-80 |
| 上野勝典・上野由貴枝:ネコノメソウ属イワボタン列を中心とした交雑種 | 81-86 |
| 上野勝典・上野由貴枝:オオバノアマクサシダ | 87-89 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(14) | 91-100 |
| 藤田淳一:長野県植物誌改訂調査で確認された県新産種の紹介 | 101-108 |
| 大塚孝一:長野県植物誌改訂 文献資料1:「北陸の植物」・「植物地理・分類研究」に掲載された植物相・植生等に関する文献目録 | 109-110 |
| 大塚孝一:長野県植物誌改訂 文献資料2:「長野県自然保護研究所紀要」・「長野県環境保全研究所研究報告」に掲載された植物相・植生等に関する文献目録 | 111-112 |
| 中村千賀:長野県植物誌改訂 研究史資料1:石澤 進 | 113-117 |
| 大塚孝一:長野県植物誌改訂 研究史資料 2:豊国秀夫 | 119-123 |
| 大塚孝一:「長野県外来植物目録(2018年版)」(長野県外来植物目録編纂委員会編)を出版しました。 | 125 |
| 松田行雄:長野県植物誌補遺(7)クモモミジイチゴの訂正 | 127 |
| 千葉悟志:高橋秀男先生を偲んで | 129-130 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2018年度大会及び218例会の報告 | 131-136 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第218回例会報告 富士見町程久保川の植物 | 137-144 |
| 藤田淳一・千葉悟志:長野県植物研究会第219-220回例会報告例会概要・高森町吉田山及び飯島町与田切渓谷の植物 | 145-155 |
2018年 No.51
| 藤井伸二・牧雅之:長野県産マダイオウの標本(国立科学博物館蔵)を見いだす | 1–2 |
| 中村千賀・林部直樹・田辺智隆・戸隠奥社の杜と杉並木を守る会: 戸隠神社奥社社叢林における毎木調査の記録 | 3-11 |
| 加藤 順:コナラ林の群落組成 | 13-16 |
| 尾関雅章・石田祐子・大塚孝一・藤田淳一・佐藤利幸: 長野県の標本資料密度:長野県植物誌改定での重点調査地区はどこに? | 17-20 |
| 土田勝義:東ヒマラヤの草原植生 | 21-27 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物ホットスポット1 | 29-30 |
| 三樹和博:長野県ササ類地図(4)木曽駒ヶ岳周辺のササ類相 | 31-34 |
| 小林正明:(報告)2017年・南信州でスズタケの広域開花について | 35-45 |
| 川上美保子:キク科トウヒレン属の新種トウミトウヒレンについて | 47-50 |
| 堤 久:松川町の天竜川河原に生育するツツザキヤマジノギクについて | 51-58 |
| 齋藤信夫:平内町浪内山におけるカラスザンショウの分布とその立地 | 59-64 |
| 落合照雄:志賀高原の腐植酸性池沼 渋池 四十八池 蓮池の珪藻類 | 65-74 |
| 飯島敏雄・永沼治:北アルプス、高天原・雲ノ平池沼群の淡水藻類について | 75-85 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(12) | 87-90 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地(11) | 91-96 |
| 松田貴子・腰原正己・藤田淳一:松本市および安曇野市で確認されたアリアケスミレViola betonicifolia Sm. var. albescens (Nakai) F.Maek. et T.Hashim. | 97-98 |
| 井浦和子:クマツヅラVerbena officinalis L.およびヒメウキクサLandoltia punctata (G.Mey.) Les et D.J.Crawfordの長野県内新産地について | 99-100 |
| 草間 勉:大町市高瀬川観音橋支柱桜公園の造成(メモ) | 101-103 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(13) | 105-116 |
| 大塚孝一・星山耕一・藤田淳一・尾関雅章・石田祐子:「長野県植物目録」補遺(1) | 117-126 |
| 大塚孝一:「長野県植物目録(2017年版)」(長野県植物目録編纂委員会編)を出版しました。 | 127 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2017年度大会及び215例会の報告 | 129-139 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第215回例会報告 安曇野市黒沢の植物 | 141-149 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会第216回及び217回例会報告 その1 | 151-153 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第216-217回例会報告 高森町松岡城址及び不動滝の植物 | 155-166 |
2017年 No.50
| 中山 冽:長野県植物研究会50周年記念誌 巻頭言 | 1 |
| 石沢 進:長野県産植物の栄村における新産地 | 3-6 |
| 岩坪美兼:長野市川中島のスイバ(タデ科)の核型変異 | 7-8 |
| 長野県産スゲ属植物の追加 | 9-12 |
| 門田裕一:霧ヶ峰のトウヒレン | 13-16 |
| 近田文弘:松本市に県立自然誌博物館建設を | 17-19 |
| 佐藤杏子・山崎貴博・岩坪美兼:長野県の亜高山帯・高山帯に分布するタンポポ属植物の染色体数・核型 | 21-22 |
| 菅原 敬:花の多型性と雌雄性の文化との関連 | 23-25 |
| 鈴木浩司:長野県におけるヒュウガセンキュウの分布とシナノノダケについて | 27-28 |
| 芹沢俊介:シシウド覚え書 | 29-30 |
| 藤井伸二・牧雅之:マダイオウと雑種ノダイオウの混乱 | 31-35 |
| 藤井紀行:長野県の高山帯の系統地理学的な重要性について | 37-38 |
| 増澤武弘:八ヶ岳における高山植物の研究課題 | 39-42 |
| 佐藤利幸:長野県植物研究会50年の歩みと動態 〜参加者記録から読み解く〜 | 43-50 |
| 林一六・加藤順:森は待機中の炭酸ガスをどのくらい吸収するのか:長野県上田市伊勢山のコナラ林の例 | 51-52 |
| 川上美保子:長野県東御市湯の丸高原の植物相 | 53-64 |
| 中山 冽:美笹ハンノキ自然園の植物目録 | 65-67 |
| 加藤 順:アカマツ林構成属及び種からみた群落組成の均質性 | 69-73 |
| 加藤 順:日本におけるススキ群落種組成の圴一性 | 75-82 |
| 三樹和博:長野県ササ類地図(3)御嶽山周辺のササ類相 | 83-85 |
| 堤 久:2016年に高森町で採集したシダ植物 | 87-94 |
| 佐藤利幸・露崎史郎・吉田静男:温帯3地点における33年間の局所シダ植物組成の維持33.3% | 95-99 |
| 松田行雄:ミズゴケ類Sphagnaceaeの絶滅危惧種の指定について | 101-112 |
| 齋藤信夫:青森県津軽地方のカラスザンショウ混交林の現状 | 113-122 |
| 飯島敏雄:北八ヶ岳、七ツ池火口湖の淡水藻類 | 123-131 |
| 落合照雄:小谷地区の池沼と姫川源流の藻類植生(珪藻類植生を主として) | 133-144 |
| 石田祐子・藤田淳一・大塚孝一:過去・現在・未来の情報源 さく葉標本 −その作成方法− | 145-152 |
| 大塚孝一:長野県産シダ植物のタイプ標本 | 153-160 |
| 藤田淳一:連続する特徴 −長野県の不可解な植物たち− | 161-163 |
| 加倉井洸美・長谷川慎平・竹重聡・松浦亮介・大杉周・佐藤利幸:希少シダ植物(ヤシャイノデ・オニイノデ)幼胞子体の葉形発達プロセスの定量比較 | 165-176 |
| 竹重 聡:センジョウデンダ(Polystichum atkinsonii )の胞子人工播種栽培成功と分布推移について | 177-180 |
| 中村千賀:エゾシロネLycopus uniflorus Michx.の匍匐枝と栄養繁殖器官についての報告 | 181-183 |
| 草間 勉:北アルプスから安曇野での桜育成の条件と実績 | 185-186 |
| 上野勝典・上野由貴枝:開田高原に自生するワサビの特徴について | 187-191 |
| 井浦和子・中村康幸:長野県飯田市で確認されたムヨウラン(Lecanorchis japonica Blume) | 193-195 |
| 松田貴子・横内文人:長野県新産植物ススヤアカバナEpilobium parviflorum Schreb.およびアレチウシノシタグサAnchusa arvensis (L.) M.Bieb.の報告 | 197-199 |
| 竹重 聡:長野県内新産地報告(4) | 201 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(12) | 203-218 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(16) | 219-220 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2016年度大会及び212例会の報告 | 221-223 |
| 大原隆明:長野県植物研究会2016年度大会(特別講演要旨)日本のサクラ・長野県のサクラ | 223-226 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第209回例会報告 陣場平山の植物 | 227-232 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会第213回及び214回例会報告 その1 | 233-234 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第213-214回例会報告 菅平湿原と菅平大洞の植物 | 235-243 |
2016年 No.49
| 田中 茂・松田行雄:霧ヶ峰車山湿原30年間の動態 | 1-7 |
| 田中 茂・松田貴子・藤森祥平:霧ヶ峰八島ヶ原湿原49年間の動態2.定置枠調査から見えてくるもの | 9-15 |
| 加藤 順・林一六:長野県上田市におけるアカマツ林伐採跡地の植生回復とコナラ林の成長 | 17-21 |
| 齋藤信夫:カラスザンショウ幼木林の種構成と立地の特徴及び成林の推測−青森県深浦町大間越の場合− | 23-30 |
| 三樹和博:長野県ササ類地図(2)長野県最南部のササ類相 | 31-34 |
| 飯島敏雄:北八ヶ岳、白駒湿原の淡水藻類について | 35-43 |
| 落合照雄:北信地方のミズゴケSphagnum湿原の藻類相−三ケ月、アワラ、カヤの平、斑尾、落倉のミズゴケ湿原の藻類− | 49-59 |
| 竹重 聡:ウロコノキシノブ(Lepisorus oligolepidus)の分布推移と胞子播種検証について | 61-66 |
| 藤田淳一:長野県におけるミチノクヨロイグサ(ケナシミヤマシシウド)Angelica sachalinensis Maxim. var. glabra (Koidz.) T.Yamaz.の生育確認と問題点 | 67-75 |
| 藤田淳一:長野県新産キヨスミギボウシHosta kiyosumiensis F.Maek.の報告 | 77-78 |
| 上野勝典・上野由貴枝:大鹿村で見つかったリンドウ科の一種 オオシカリンドウ(仮称) | 79-81 |
| 吉沢敏江:白馬・小谷の植物覚え書き | 83-86 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(11) | 87-89 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地(10) | 91-94 |
| 草間 勉:天然記念物の桜の創造(4)高瀬川観音橋西河川敷支柱桜公園作りと野生桜育成活動のまとめ | 95-97 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(11) | 99-110 |
| 林 一六:本の紹介:「日本の風穴」清水長生・澤田結基著 | 111 |
| 佐藤利幸:大平仁一さんへの追悼エッセイ | 113 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2015年度大会及び209例会の報告 | 115-120 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第209回例会報告 | 121-128 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会第210回及び211回例会報告 その1 | 129-130 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第210-211回例会報告(その2)蓼科高原の植物 | 131-139 |
2015年 No.48
| 中山 冽:長野県植物研究会と清水建美先生 | 1-3 |
| 三樹和博:長野県ササ類地図(1)八ヶ岳を巡る二つの交雑帯 | 5-8 |
| 小山泰弘・尾関雅章:横手山鉱山跡地の植生回復 | 9-14 |
| 加藤 順・川上美保子・植松直樹・今井俊枝・垣内雄治・垣内美佐子:霧ヶ峰草原の植物生態学的研究2:攪乱(刈取)がユウスゲの生育に与える影響 | 15-18 |
| 加藤 順・川上美保子:霧ヶ峰草原の植物生態学的研究3:Rao’s quadratic diversity indexによって算出された時間空間的階層構造の度合いと草本群落の二次遷移のステージの関係 | 19-24 |
| 篠原義典・服部充・市野隆雄:長野県におけるキツリフネImpatiens noli-tangere L.(Balsaminaceae)の開花フェノロジーと株あたり花数にみられる二型 | 25-28 |
| 服部充・山本哲也・市野隆雄:長野県中部におけるツリフネソウImpatiens textorii Miq.(Balsaminaceae)の訪花昆虫 | 29-30 |
| 千葉悟志・尾関雅章:フクジュソウの種子発芽特性からみるアリによる種子散布の意義について | 31-37 |
| 齋藤信夫:沖舘川多目的湧水地に進入しているクロバナエンジュ(Amorpha fruticosa L.)の現状について | 39-44 |
| 飯島敏雄:北八ヶ岳、地獄谷の一時的火口湖の珪藻類について | 45-53 |
| 落合照雄:霧島火口群の火口湖と恐山湖の珪藻類 | 55-66 |
| 蛭間 啓・南信州植物調査会・大鹿の100年先を育む会:長野県南部地域における植物の分布記録 | 67-70 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(10) | 75-77 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地(9) | 79-80 |
| 竹重 聡:長野県内新産地報告(3) | 81-82 |
| 藤田淳一・小澤正幸:長野県新産植物3種の報告 | 83-86 |
| 大平仁一:植物エッセイ | 87-90 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(10) | 93-100 |
| 金井弘夫ほか:清水建美先生 思い出の記 | 101-108 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2014年度大会及び206例会の報告 | 109-114 |
| 東 浩司:長野県植物研究会2014年度大会(特別講演要旨)長野県産セリ科シシウド属植物の分類学的問題点について | 115-116 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第206回例会報告(その2)黒姫高原の植物 | 117-122 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会第207回及び208回例会報告 その1 | 123-124 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第207-208回例会報告(その2)木曽町・王滝村の植物 | 125-132 |
2014年 No.47
| 小山泰弘・仙石鐡也:松本市牛伏寺の植物相 | 1-9 |
| 川上美保子:延焼後の霧ヶ峰池のくるみの植物相 | 11-21 |
| 加藤 順・中川瑠美・川上美保子:霧ヶ峰草原の植物生態学的研究1:攪乱の影響を定量化するために提唱されたIndex of dynamic statusの汎用性 | 23-28 |
| 齋藤信夫:青森県東部海岸付近の植生 | 29-48 |
| 田中 茂・松田貴子・藤森祥平:霧ヶ峰八島ヶ原湿原49年間の動態1.帯状測定から見えてくるもの | 49-59 |
| 落合照雄:唐花見湿原 親海湿原の藻類相 | 61-76 |
| 北沢あさ子:ハナノキ湿地周辺の絶滅危惧植物の発見・6 | 85-88 |
| 上野勝典・上野由貴枝:御嶽山周辺に産するネコノメソウ属の一種オンタケネコノメソウ(新称) | 89-93 |
| 川上美保子・加藤順・星山耕一:長野県新産植物ゴマノハグサ科サツキヒナノウスツボScrophularia musashiensisの記録 | 95 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(9) | 97-100 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地(8) | 101-103 |
| 竹重 聡:長野県内新産地報告(2) | 105-107 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記(11) | 109-112 |
| 松田貴子・桜井智子:松本市山と自然博物館に修造されている植物標本の概要 | 113-114 |
| 大平仁一:植物エッセイ | 115-118 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(9) | 119-130 |
| 大塚孝一:故今井建樹先生の足跡 | 131-132 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2013年度大会及び204例会の報告 | 135-141 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第204回例会報告(その2)烏川渓谷(小野沢川沿い)の植物 | 143-150 |
| 蛭間 啓:長野県植物研究会第205回例会報告 | 151-155 |
2013年 No.46
| 藤間峻亮・齋藤風菜・大窪久美子・百原新・沖津進:霧ヶ峰高原における小丘地形の立地環境と植物群落の関係 | 1-9 |
| 冨田美紀・水永優紀・増澤武弘:長野県霧ヶ峰におけるニッコウキスゲの発芽生理特性 | 11-14 |
| 土田勝義・川上美保子・星山耕一:霧ヶ峰の植物相 | 15-37 |
| 齋藤信夫:岩木川河口付近河川堤防の植生の変化 −2008年と2012年の比較から− | 39-47 |
| 星山耕一・川上美保子:長野県東御市池の平周辺の植物相 | 49-57 |
| 飯島敏雄:キタ八ヶ岳茶水の池の淡水藻類 | 59-70 |
| 落合照雄:居谷里湿原の珪藻類 | 71-83 |
| 小口好久:八ヶ岳唐沢鉱泉の源泉池に見られる生物相 | 85-87 |
| 大塚孝一:長野県におけるベニシダの分布Ⅱ −西暦2000年から約10年後の分布変化 | 89-93 |
| 廣江伸作:茶臼山高原及び周辺地域の植物雑記 | 95-97 |
| 北沢あさ子:ハナノキ湿地周辺の絶滅危惧植物の発見・5 | 99-100 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記(10) | 101-108 |
| 堤 久・前島道広・熊谷久一:南アルプスにおける絶滅危惧種ヤシャイノデの保護回復事業報告 | 109-114 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(8) | 115-118 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地(7) | 119-123 |
| 竹重 聡:長野県内新産地報告(1) | 125-126 |
| 横井 力・中山冽・尾関雅章・大塚孝一:長野県環境保全研究所標本庫(NAC)で記録された長野県新産植物 | 127-128 |
| 大平仁一:植物エッセイ | 129-135 |
| 和田 清:奥裾花のユキツバキ後日談 | 137 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(8) | 139-149 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2012年度大会及び201例会の報告 | 151-154 |
| 中村千賀・藤田淳一:長野市荒倉山小倉沢の植物(第201回例会報告その2) | 155-158 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第202回・203回例会報告(その2)八千穂植物園(佐久穂町)・榊山国有林(佐久市)の植物 | 161-168 |
2012年 No.45
| 落合照雄:居谷里ミズゴケ湿原のツヅミ藻相 緑藻相 藍藻相 | 1-10 |
| 飯島敏雄:三峰川の珪藻 | 11-18 |
| 齋藤信夫:青森県津軽半島周辺の海岸植生と分布 | 19-33 |
| 廣江伸作:茶臼山植物雑記 | 35-38 |
| 北沢あさ子:ハナノキ湿地周辺の絶滅危惧植物の発見・4 | 39-41 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(7) | 43-46 |
| 大平仁一:植物エッセイ | 47-51 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(7) | 53-63 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(15) | 65 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2011年度大会及び198例会の報告 | 67-70 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第198例会報告 | 71-78 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会第199回及び200回例会の報告 その1 | 79-80 |
| 藤田淳一:白馬村塩島城址及び平川谷の植物(第199回及び200回例会の報告 その2) | 81-86 |
2011年 No.44
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究20長野県に生育する植物の開花と標高の関係の季節変化と開花型の提唱 | 1-11 |
| 齋藤信夫:津軽地方の丘陵地帯に発達するニセアカシア優占林の種構成や階層構造の特徴 | 13-25 |
| 飯島敏雄・長尾孝之:御岳山火口湖群の淡水藻類について Ⅳ 緑藻類 | 27-30 |
| 北沢あさ子:ハナノキ湿地周辺の絶滅危惧植物の発見・3 | 31-32 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(6) | 33-36 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地(6) | 37-40 |
| 大平仁一:植物エッセイ | 41-46 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(6) | 47-58 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(14) | 59 |
| 松田行雄:長野県植物誌補遺 長野県産ミズゴケ類(Sphagnum L.)143-16頁の追加、訂正 | 61-64 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2010年度大会及び195例会の報告 | 65-66 |
| 藤田淳一:長野県植物研究会第195例会報告 | 67-68 |
| 名取 陽・坂口竣弥・小口好久:長野県植物研究会 第196回及び197回例会の報告 | 69-75 |
2010年 No.43
| 川上美保子・越石俊江・柴平志保子・原千枝子・吉村素野香:長野県霧ヶ峰高原池のくるみ地区における火入れ一年目の植生 | 1-6 |
| 田中 茂・松田行雄・松田貴子:霧ヶ峰湿原の植生の現況1 踊場湿原10年間の動態 1998〜2008 | 7-12 |
| 齋藤信夫・竹内健悟・齋藤宗勝:岩木川下流域の河川敷に広がるヨシ原の群落区分及び群落と土壌や人的攪乱との関係 | 13-18 |
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究19 西駒ヶ岳千畳敷の開花フェノロジー | 19-28 |
| 飯島敏雄・長尾孝之:御岳山火口湖群の淡水藻類について Ⅲ 四ノ池・五ノ池の珪藻類 | 29-42 |
| 落合照雄:志賀高原(長野県北東部)一沼の藻類相 | 43-50 |
| 平田聡子・齋藤信:小諸市御影新田における「こもろミズオオバコビオトープ」の環境整備について | 51-54 |
| 北沢あさ子:ハナノキ湿地周辺の絶滅危惧植物の発見・2 | 55-58 |
| 中澤清人・川上美保子:イチョウウキゴケの発見 | 59-62 |
| 竹重 聡:長野県内キヨズミオオクジャクの新産地報告 | 63-64 |
| 竹重 聡:オオカワヂシャの繁殖要因と生物多様性 | 65-68 |
| 横内文人・山田和男:セイヨウタンポポが燕岳へ登山した | 69 |
| 大平仁一:植物エッセイ | 71-77 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(5) | 79-89 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(13) | 91-92 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2009年度大会及び192例会の報告 | 93-98 |
| 島野光司:長野県植物研究会193回ならびに194回例会の報告 | 99-102 |
2009年 No.42
| 松浦亮介・佐藤利幸:長野県シダ植物種密度と植生帯タイプとの対応 | 1-4 |
| 藪田泰基・佐藤利幸:日本産ダイコンソウ属の種子形態比較 | 5-7 |
| 飯島敏雄・長尾孝之:御岳山火口湖群の淡水藻類について Ⅱ 二ノ池・三ノ池の珪藻類 | 9-19 |
| 梅澤 芳:増沢武弘:八ヶ岳におけるコマクサ純群落の成立要因 | 21-28 |
| 尾鼻陽介・清水ゆかり:北アルプス朝日岳におけるハクサンコザクラの異型花柱性について | 29-30 |
| 小山泰弘・加藤輝和:牛伏川流域でニセアカシアが増えたわけ | 31-38 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県における新種トヨボタニソバについて | 39-42 |
| 名取 陽・伊藤一成・神幸夫:野生ホテイアツモリソウ(Cypripedium macranthos var. hotei-atsumorianum)の生育および人工授粉による結実について | 43-46 |
| 平田聡子・齋藤信:小諸市御影新田におけるミズオオバコOttelia japonica等の移植保全について | 47-49 |
| 竹重 聡:千曲川右岸スギ林のシダ新産地の環境特性 〜イノデ類とイワヘゴの記録経緯と分布拡大を考える | 51-62 |
| 北沢あさ子:ハナノキ湿地周辺の絶滅危惧植物の発見 | 63-64 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(5) | 65-69 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地(5) | 71-74 |
| 横内文人:塩尻市のヒマラヤスギと北アルプス種池のミズバショウ | 75 |
| 大平仁一・大平ユリ:植物エッセイ | 77-80 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(4) | 81-89 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(12) | 91-92 |
| 堤 久・小林正明:<秋季例会報告>大鹿村(塩河・鳥倉林道)観察会(187・188回例会) | 93-94 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会2008年度大会及び189回例会の報告 | 95-100 |
| 原千恵子・川上美保子:上田市大洞ブナ林と蝶が原林道方面植物観察会(190・191例会)報告 | 101-107 |
2008年 No.41
| 佐藤利幸ほか:新松本市の植物多様性とシダ植物相 | 1-10 |
| 田中崇行・佐藤利幸:亜熱帯性シダ植物の北進?(名古屋市モエジマシダと松本市のホウライシダ) | 11-17 |
| 上野勝典・上野由貴枝:塩尻市の暖地性シダとカタイノデの生育状況 | 19-23 |
| 飯島敏雄:伊那市新山の湿原の淡水藻類植生(2)珪藻類 | 25-36 |
| 名取 陽:八ヶ岳連峰におけるダケカンバおよびシラカンバの分布と生態 | 37-46 |
| 井浦和子:長野県高山村におけるカイサカネランの新産地 | 47-48 |
| 大平仁一:植物エッセイ | 49-61 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(3) | 63-77 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(11) | 79-80 |
| 大塚孝一:長野県植物研究会の展望一会員のつぶやき | 81 |
| 長野県植物研究会40周年記念大会記録 | 83 |
| 名取 陽・坂口竣弥・小口好久:[例会報告]八ヶ岳西岳と釜無方面植物観察会(182・183例会)報告 | 85-87 |
2007年 No.40
| 加藤 順・林一六:菅平におけるアカマツ群落の遷移 | 1-13 |
| 川上美保子:上田市舞田峠におけるアカマツ伐採跡地の植生変化 | 15-18 |
| 尾関雅章・土田勝義:八方尾根蛇紋岩地における地質境界付近の植生変化 | 19-23 |
| 齋藤信夫:六ヶ所丘陵の潜在自然植生の推測 | 25-36 |
| 馬場多久男:南箕輪村田畑半沢における植生管理の提案 | 37-45 |
| 土田勝義・土田恵理:安曇野における主な屋敷林の植生 | 47-55 |
| 武井 尚:南佐久郡北相木村の植生 | 57-58 |
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究16 −軽井沢町塩沢地区の虫媒花の開花種類数の季節変化− | 59-70 |
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究17 −立科町女神湖周辺の虫媒花の開花フェノロジーについて | 71-81 |
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究18 −コウゾリナPicris hieracioides subsp. japonicaの開花と標高について | 83-88 |
| 松田貴子・桜井智子・酒巻裕三:千曲市で発見されたマルミノウルシ(Euphorbia ebracteolataHayata)の生育環境 | 89-97 |
| 小山泰弘・松澤義明・星山耕一・神林清文・本藤美歩:大川入山のイラモミ | 99-101 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県で見つかったトウノウネコノメ | 103-105 |
| 土屋 守:タカネヒゴタイの白花品 | 107 |
| 高橋美穂子・菅原 敬:日本産ハコベ属の種子表面構造と分類形質としての有効性 | 109-116 |
| 堤 久:長野県産シダ植物の分布図集 | 117-135 |
| 佐藤利幸:信州におけるシダ植物種密度の水平分布図作成の試み | 137-139 |
| 中村武久:北アルプスと南アルプスのシダフロラ | 141-148 |
| 横内文人:アメリカスズカケが帰化している | 149 |
| 大塚孝一・尾関雅章・宮入盛男:特定外来生物オオカワジシャ(ゴマノハグサ科)の千曲市における自生確認 | 151-153 |
| 浅野一男:下伊那産帰化植物初採集標本目録 | 155-167 |
| 金井弘夫:帰化植物の都道府県別種類数 CD-ROM長野県植物誌資料集の利用例 | 169-171 |
| 飯島敏雄:伊那市新山の湿原の淡水藻類植生(1)緑藻類 | 173-180 |
| 橋渡勝也・友野増夫・中山厚志:北佐久地方で採集された大正時代の植物標本 | 189-192 |
| 名取 陽:絶滅か再生か・釜無,入笠山 アツモリソウの危機 | 193-196 |
| 竹重 聡:50余年の歳月を経て行方沼東,倉田悟の短歌見つかる 遠山川北又澤伐採事業所視察者芳名録より | 197-198 |
| 大平仁一:飯山の山奥には宝の植物がある,他 | 195-205 |
| 小橋寿美子・藤井紀行・岡秀一:ブナの地理的変異研究と今後の展望 | 207-213 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(2) | 215-227 |
| 竹重 聡:上高地(田代池〜明神館)の主なシダ植物 | 229-232 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(4) | 233-236 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地(4) | 237-240 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(10) | 241-244 |
| 横内文人:〔2006年度夏季例会報告〕梓川,島々谷の植物観察会(180・181例会) | 245-246 |
| 戸谷彌生:〔2007年度夏季例会報告〕唐花見湿原・居谷里湿原・親海湿原植物観察会2007年度総会と180・181例会報告 | 247-250 |
2006年 No.39
| 小澤正幸・溝口智秋:軽井沢・碓氷峠におけるマムシグサ類の観察記録−ヤマジノテンナンショウとヤマザトマムシグサの比較を中心として− | 1-4 |
| 千葉悟志・清水建美:コマクサの生活史および繁殖特性−日本産草本植物の生活史研究プロジェクト報告第6報− | 5-13 |
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究15 −飯田市と軽井沢町の開花フェノロジーと同一種の開花日の地域による差について− | 15-42 |
| 齋藤信夫:沖舘川多目的遊水池の植生と今後の動向の推測 | 43-50 |
| 加藤 順・林一六:日本におけるアカマツ群落の種類組成と温度環境 | 51-62 |
| 飯島敏雄:諏訪湖流入河川の珪藻類(2) | 63-73 |
| 竹重 聡:「小泉源一によるセンジョウデンダ日本初記録」その年代場所に迫る | 75-78 |
| 横内文人:故・小泉秀雄先生の野帳(1) | 79-97 |
| 横内文人・土田勝義:長野県の帰化植物目録 | 99-119 |
| 小林正明:シラカンバの雌雄モザイク | 121 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地(3) | 123-127 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(3) | 129-130 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(9) | 131-132 |
| 大平仁一:蓮の寺(稲泉寺)の大葉菩提樹,山シャクヤクの育成と種の色,山ゆりの群生地に会う | 133-137 |
| 伊藤静夫・中山冽:〔夏季例会報告〕戸隠の観察会(176・177例会) | 140-141 |
| 田中光枝:〔秋季例会報告〕大桑村阿寺渓谷・南木曽町柿其渓谷の植物観察会(178・179例会) | 142 |
| <要望書>絶滅危惧植物ハナヒョウタンボク(Lonicera maackii)の保護に関する要望書 | 143 |
2005年 No.38
| 小泉武栄:風食による植被の破壊がもたらした強風地植物群落の種の多様性 −飯豊山地の偽高山帯における事例− | 1-9 |
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究14 −夏・秋咲き植物10種の開花と標高− | 11-18 |
| 増沢武弘・梅津裕里:八ヶ岳の高山植物群落Ⅰ −岩礫地に生育するイワヒゲの生育特性 | 19-23 |
| 佐藤孝幸・渡辺隆一:シラカンバの個体構造と物質生産 | 25-28 |
| 千葉悟志・清水建美:長野県絶滅危惧ⅠB類ビッチュウフウロの生活史および開花特性 −日本産草本植物の生活史研究プロジェクト報告第5報 | 29-32 |
| 川上美保子・海野芙美子・小野遊子・越石俊江・染野俊哉・渋沢美佐緒・野口喜久子・野々村孝子・村山顕:長野県青木村のブナ群落 | 33-35 |
| 池田登志男・川上美保子・渋沢美佐緒・篠原修・藤倉佑子・富士田裕子・三井幸子・林一六:長野県上田市産モイワナズナの生物学 | 37-42 |
| 宋 立軍・佐藤利幸:サラシナショウマの葉節間の個体内分化の定量形態学 | 43-47 |
| 飯島敏雄:諏訪湖流入河川の珪藻類(1) | 49-60 |
| 小山泰弘:長野県内におけるササ開花情報(6)−2004年− | 61-64 |
| 小山泰弘・丸山勝規・稲村昌弘・土橋幸作:波田学院の森(東筑摩郡波田町)の大径木 | 65-69 |
| 柴田 治・岩岡安民・小林武夫・塩原道雄・高橋新吾:長野県美ヶ原草原(海抜2000m)で見られたアースハンモック構造土 | 71-72 |
| 金井弘夫:長野県植物誌資料集による「資料密度」 | 73-75 |
| 大塚孝一:故横内斎先生採集の長野県産シダ植物 | 77-85 |
| 横内文人:八ヶ岳の高山植物 | 87-94 |
| 浅野一男:「長野県植物誌」(1997)に追加される下伊那地方産の植物(2) | 95-113 |
| 浅野一男:下伊那教育会館所蔵維管束植物標本目録1 | 115-126 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(8) | 127-131 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地(2) | 133-136 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告(2) | 137-138 |
| 松永守祐:西(木曽)駒ヶ岳,八ヶ岳の高山植物と思い出 | 139-141 |
| 大平仁一:栄村の植物と私の大切なヒメカイウ | 142 |
| 本の紹介:清水敏一「大雪山の父・小泉秀雄」(金井弘夫) | 143 |
| ニュース:長野県植物誌資料集CD-ROM完成 | 144-145 |
| 川上美保子:<夏季例会報告>坂井村と青木村の植物観察(172・173例会) | 147-148 |
| 田中光枝・輿石俊江:川上村の植物観察会(174・175例会) | 149-150 |
2004年 No.37
| 千葉悟志・清水建美:長野県絶滅危惧ササユリの生活史および訪花昆虫 | 1-8 |
| 小山泰弘:長野県内におけるササ開花情報(5)〜2003年〜 | 9-12 |
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究10 ノイバラの開花と標高について | 13-20 |
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究11 ツリガネニンジンの開花と標高について | 21-27 |
| 飯島敏雄:駒ヶ根市、大沼湖及び駒が池の珪藻類 | 29-37 |
| 竹重 聡・大塚孝一・堤 久:センジョウデンダ(オシダ科)の新産地 | 39-43 |
| 上野勝典・上野由貴枝:長野県産シダ植物の新産地 | 45-48 |
| 上野勝典・上野由貴枝:新産地報告 | 49-50 |
| 横内文人:日本南アルプスの高山植物(2) | 51-72 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(7) | 73-80 |
| 大塚孝一・尾関雅章・栩秋隆哉:長野県希少野生動植物保護条例の規定により希少野生動植物 | 81-84 |
| 秋本眞澄:長野県のミヤマニガウリ | 85-101 |
| 大平仁一:花の女王「ニリンシラネアオイ」を見つめて | 103 |
| 橋渡勝也:<春季植物観察会報告>:堀金村の植物観察(第168・169回例会) | 105-106 |
| 堤 久・小林正明:<秋季例会報告>上村下栗の植物観察会(170・171例会) | 107-108 |
| 大塚孝一:<訂正>NO.36(2003)21p.の差し替え(ナベクラザゼンソウの葉形と根茎の位置) | 109 |
2003年 No.36
| 横内文人:日本南アルプスの高山植物(1) | 1-20 |
| 大塚孝一:ナベクラザゼンソウの葉形と根茎の位置 | 21-24 |
| 小山泰弘:長野県内におけるササ開花情報(4)〜2001、2002年〜 | 25-26 |
| 川上美保子・渋沢美佐緒:大岡村の植物標本リスト | 27-34 |
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究(Ⅶ) ノコンギクの開花と標高について | 35-42 |
| 小林正明:信州の植物フェノロジーの研究(Ⅷ) クリのフェノロジーと標高について | 43-50 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(6) | 51-59 |
| 金井弘夫:CD-ROM長野県植物誌資料集テスト版始末 | 61-68 |
| 飯島敏雄:駒ヶ根市南割総合運動場わきの湿地の淡水藻類 第1報 | 69-80 |
| 中山 冽:残したい信濃の自然(その2)−水田雑草の事例− | 81-84 |
| 竹重 聡:ウロコノキシノブの自生地環境分布に応じた形状特性 | 85-92 |
| 竹重 聡:長野県におけるウロコノキシノブの分布と生態への考察(1) | 93-100 |
| 小林正明:シロバナクズを上村で記録 | 101-102 |
| 中山 冽:野辺山・矢出川湿原植物観察会 〜2002年度総会と164・164例会報告〜 | 103-104 |
| 上松征子:奥信濃「秋山郷の植物」観察会の報告 | 105-108 |
| 野口スナオ:秋山の例会に参加して 「大秋山部落の滅亡について」 | 109 |
| 石澤滋子:私のまちの宝 「正受老人と正受庵」 | 111-114 |
| 大平仁一:秋山郷の文化(1)「のよさ節」について | 115-119 |
2002年 No.35
| 飯島敏雄:天竜川の珪藻類 | 1-15 |
| 井田秀行・川上美保子:菅平高原大洞地区に残存するブナ孤立林の森林構造 | 16-19 |
| 名取 陽:八ヶ岳高山帯におけるイワベンケイおよびタカネツメクサの温度環境 | 20-24 |
| 浅野一男・林一六・平林国男・伊藤静夫・中山冽・清水建美・土田勝義:長野県菅平湿原の植物生態2.群落構造 | 25-29 |
| 中谷 冽・松田行雄:北極圏の植物と群落(北欧植物紀行) | 30-38 |
| 横内文人:日本中央アルプスの高山植物(2) | 39-52 |
| 浅野一男:「長野県植物誌」(1997)に追加される下伊那地方産の植物(1) | 53-62 |
| 中山 冽:残したい信濃の自然(その1)−水田土手植生の事例− | 63-64 |
| 大平仁一:カヤノ平と高標山登山 | 65 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(5) | 66-68 |
| 奥原弘人:ツツジの雑種 | 69 |
| 清水建美:奥原弘人先生を悼む | 70 |
| 松田行雄:奥原弘人先生の思い出 | 71-72 |
| 佐藤利幸:162回0回記録の報告(松本市美ヶ原高原の散策) | 74-75 |
| 楯 誠治:<秋季例会報告>小路峠と阿寺渓谷の植物観察会 | 75-76 |
2001年 No.34
| 樋口美香・土田勝義:松本市街地における樹林の現状と評価 −ビオトープの観点から | 1-10 |
| 友野増夫・林一六:東信地区におけるスゲ属の分布 | 11-24 |
| 大塚孝一:長野県におけるベニシダの分布 | 25-34 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記 (9) | 35-40 |
| 飯島敏雄:御岳山火口湖群の淡水藻類 Ⅰ珪藻類 | 41-45 |
| 横内文人:植物ニュース(オクハラツメクサ、ハマクサギ) | 46 |
| 小山泰弘:長野県内におけるササ開花情報(3)−2000年 | 47-48 |
| 横内文人:日本中央アルプスの高山植物(1) | 49-62 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(4) | 63-70 |
| 清水建美:長野県植物誌資料集の出版に向けて −長野県植物誌資料集作成委員会の報告 | 71-72 |
| 柴田 治:故山﨑林治先生を偲んで | 73-74 |
| 岩見啓子:飯山の『塩の道」と秋山郷の「御宝木」の植生と生態の観察会に参加し | 75-76 |
| 大平仁一:北信地方の主な植物分布 | 77 |
2000年 No.33
| 松田行雄・波田善夫:湿原の発達と群落の消長 2.泥炭解析による群落遷移と定置枠内の群落変化 | 1-16 |
| 境 徹:和田清:長野県内の温量指数分布 | 17-20 |
| 小山泰弘・南澤仁:台湾におけるタイワンヒノキ及びベニヒの現状 −阿里山を中心として | 21-26 |
| 小山泰弘:長野県内におけるササ開花情報(2)−1999年 | 27-30 |
| 横内文人:日本北アルプスの高山植物(3) | 31-47 |
| 北條慎一:暖温二帯の樹木 | 48 |
| 飯島敏雄:風吹大池火口湖群の淡水藻類 Ⅱ 珪藻類 | 49-59 |
| 松島隆志・徳増征二:菅平における浮泡中の水生不完全菌類相とその季節変化 | 60-66 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(3) | 67-69 |
| 中山 冽:キリギシ山に植物を訪ねて | 70-72 |
| 和田 清:信毎賞の受賞報告 | 73-74 |
| 小澤正幸:<夏季例会報告>大岡村の植物観察会 | 75 |
1999年 No.32
| 松田行雄・田中茂:湿原の発達と群落の消長 1.霧ヶ峰八島ヶ原湿原36年間の動態 | 1-19 |
| 加藤 順・林一六:相互作用する系としてのアカマツ群落の構造 | 20-23 |
| 横内文人:日本北アルプスの高山植物(2) | 24-42 |
| 今井建樹:長野県の植物覚書 | 43-46 |
| 齋藤信夫:青森市のスギ林に出現するシダ植物とその傾向 | 47-51 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記 (8) | 52-54 |
| 早坂祥彦:松本市藤井沢のハミズゴケとシッポゴケの生態観察 | 55-59 |
| 小山泰弘:長野県内におけるササ開花情報 | 60-63 |
| 小澤正幸・野口達也:長野県北部のトリゲモ類(イバラモ科) | 64-66 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺(2) | 67-69 |
| 横内文人:ケショウヤナギの新しい分布地(4)−大町市籠川− | 70 |
| 奥原弘人:「長野県植物誌」二帯する所感,木曽のヤクシマヒメアリドオシラン Vexillabium yakushimense | 71-72 |
| 植物ニュース:ヒメフウロ・シオヤキソウ(横内文人),ユウシュンラン(霜田芳武),ミドリヒメザゼンソウ(川上美保子・渋沢美佐緒) | 73 |
| 松田行雄:樺太湿原紀行(1997年5月26日−6月2日) | 74 |
| 清水建美:CD-Rom紹介−金井弘夫「地図で見る 日本地名索引−中部ブロック版」 | 75 |
| 中山 冽:<夏季例会報告>八千穂高原の植物観察会 | 76-77 |
| 浅野一男:<秋季例会報告>三信国境茶臼山の植物観察会 | 77-78 |
1998年 No.31
| 高橋 勧:長野県飯山地方の植物 | 1-6 |
| 川上美保子:長野県大岡村のブナ群落 | 7-9 |
| 横内文人:日本北アルプスの高山植物(1) | 10-15 |
| 今井建樹:長野県の植物覚書 | 16-19 |
| 飯島敏雄・永沼治:鎌池湿原(八方尾根)の藻類 | 20-31 |
| 浅野一男・北澤あさ子:ホザキヤドリギの長野県新産地 | 32-33 |
| 横内文人:ケショウヤナギの新しい分布地(3)−堀金村烏川と池田町高瀬川− | 34-35 |
| 奥原弘人:ヤナギの間種と野麦峠のアザミ | 36-37 |
| 目沢民雄・遠藤信元:長野県菅平におけるオキナグサの調査報告 | 38-39 |
| 清水建美(編):「長野県植物誌」補遺 | 40-43 |
| 村田 源:書評「長野県植物誌」 トラノオジソとレモンエゴマによせて | 44-45 |
| 金井弘夫:長野県植物誌データベースの今後 | 46-47 |
| 金井弘夫:長野県植物誌の未確認種について | 47 |
| 大平仁一:[夏季例会報告]鍋倉山・黒倉山の植物観察会 | 48-49 |
1997年 No.30
| 芹沢俊介:長野県のテンナンショウ属 | 1-15 |
| 大平仁一:白根葵の生育戦略 | 15-16 |
| 児玉宣子・菅原敬:乗鞍岳で確認されたコバイケイソウとバイケイソウの雑種 | 17-22 |
| 林 一六・和田瑞穂・坪本なおみ:二次遷移草本期優占種の発芽 | 23-26 |
| 今井建樹:コハクランKitigorchis itoana F.Maek.の観察記録 | 27-32 |
| 今井建樹:トラキチラン Epipogium aphyllum Sw.の観察記録 | 33-37 |
| 今井建樹:長野県の植物覚書 | 38-40 |
| 横内文人:ケショウヤナギの新しい分布地(2)−波田町黒川− | 41-42 |
| 植物ニュース:キソキバナアキギリ(奥原弘人),キンモウワラビ(池田登志男) | 42 |
| 飯島敏雄:風吹大池火口湖群の淡水藻類 Ⅰ 血の池 | 43-51 |
| 植物ニュース:ヤクシマヒメアリドオシラン(奥原弘人) | 52 |
| 金井弘夫:長野県植物誌データベース始末記 | 53-58 |
| 植物ニュース:ヒロハヌマガヤ・シナノアキギリ(篠原修・宮下昇三郎・池田敏雄) | 58 |
| 川上美保子:横沢末木氏採集植物標本目録 | 59-62 |
| 橋渡勝也:[夏季例会報告]木曽郡木祖村の植物観察会 | 63 |
1996年 No.29
| 菅原:敬:乗鞍岳に生育するコバイケイソウ及びバイケイソウの性表現・花生態に関する研究 | 1-8 |
| 林 一六・坪本なおみ:ブナ・ミズナラ陽樹の生育型と生態特性 | 9-16 |
| 今井建樹:長野県伊那地方で報告されているヤマジノギク(アレチノギク)について | 17-20 |
| 今井建樹:長野県の植物覚書 | 21-24 |
| 川角宏高・井上健:長野県におけるフクジュソウとミチノクフクジュソウの分布について | 25-28 |
| 井上 健:ハナノキ(カエデ科)の繁殖生態 | 29-32 |
| 白井幸長:[植物ニュース]丸子町のシダレグリ | 32 |
| 橋渡勝也:帰化植物アライトツメクサの新たな分布 | 33-36 |
| 橋渡勝也:[植物ニュース]ハイイロヨモギ・ケショウヤナギ | 36 |
| 飯島敏雄:諏訪の珪藻 Ⅲ | 37-43 |
| 井上 健:長野県の絶滅危惧植物調査報告 | 44-46 |
| 池田登志男:浅間山の植物 | 47-55 |
| 井上 健:[例会報告]上村日影岩の植物 | 56-57 |
| 池田登志男:[夏季例会合宿調査報告] 湯の丸山・烏帽子岳の植物観察 | 57-58 |
1995年 No.28
| 橋渡勝也:”ミソガワソウ”の由来を検討する | 1-5 |
| 橋渡勝也:[植物ニュース]長野県に新たに加わる帰化植物−アライドツメクサ | 6 |
| 白井幸長:[植物ニュース]丸子町のシダレエノキ | 7 |
| 白井幸長:[植物ニュース]上田染丘高校のフジバカマ | 8 |
| 元島清人:センジョウスゲ・マンシュウクロカワスゲの発見 | 8 |
| 相馬 潔・山本雅道・吉田利男・清水建美・豊国秀夫:ハイマツ球果および種子の生産と消失 | 9-18 |
| 林 一六・鞠子茂:オキナグサとエンビセンノウの種子サイズと発芽 | 19-21 |
| 宮下昇三郎:「なんじゃもんじゃ」という樹木 | 22-24 |
| 今井建樹:長野県の植物覚書 | 25-28 |
| 石原敏行:白馬村の植物2種 | 29 |
| 高橋 弘:岐阜県の植物 | 29-31 |
| 飯島敏雄:八方池(八方尾根)の珪藻類 | 32-38 |
| 池田登志男・高橋秀男・友野増夫・中山冽:御座山の植物目録 | 39-51 |
| 栗田正秀:植物解剖学形態学用語雑録 Ⅸ | 52-55 |
| 元島清人:[例会調査報告]木曽郡王滝村の植物観察会 | 56 |
| 池田登志男:[夏季例会合宿調査報告] 御座山の植物観察会 | 57 |
| 小沢正幸:[夏季例会報告]天狗原山の植物観察会 | 58 |
1994年 No.27
| 林 一六:ホンジェラスの森林植生と薪炭問題 | 1-8 |
| 井上 健:トガクシショウマ(メギ科)の繁殖生物学 | 9-15 |
| 齋藤信夫:津軽地方におけるブナ林の種組成と階級構成 | 16-24 |
| 飯島敏雄・永沼治・濱篤:諏訪の珪藻 Ⅱ | 25-30 |
| 名取 陽:赤道下高山における巨大ロゼット植物の温度変化 | 31-35 |
| 今井建樹:長野県植物覚書 | 36-38 |
| 菅原 敬:ミヤマアオイには二倍体と三倍体が存在する | 39-41 |
| 栗田正秀:植物解剖学形態学用語雑録 Ⅵ | 42-44 |
| 金井弘夫:長野県植物誌データベースことはじめ(その2) | 45-48 |
| 奥原弘人:着生植物についての思い出 | 49-51 |
| 奥原弘人:アザミの雑種についての補記 | 51 |
| 横内文人:[長野県植物誌 資料Ⅺ]「レポート 日本の植物」に掲載されたフロラ関係文献目録 | 52 |
| 井上 健:[夏季例会報告] 諏訪湖の植物観察会 | 53 |
1993年 No.26
| 井上 健・鷲谷いづみ・倉本宣:長野県希少植物の保全に関する研究覚書 | 1-4 |
| 林 哲也:船越眞樹:「ビーナスライン」沿いに播種されたイタチハギの分布と現状 | 5-12 |
| 菅原 敬:三型花柱性エゾミソハギの形態および花粉生産量 | 13-16 |
| 横内文人:ケショウヤナギの新しい分布地 −穂高町中房川の上流− | 17-19 |
| 飯島敏雄・永沼治・濱篤:諏訪の珪藻 Ⅰ | 20-27 |
| 池田登志男:佐久の植物分布図 (3) | 28-33 |
| 栗田正秀:植物解剖学形態学用語雑録 Ⅳ | 34-36 |
| 金井弘夫:長野県植物誌データベースことはじめ(その1) | 37-39 |
| 奥原弘人:挿し木を勧める | 40 |
| 北條慎一:接ぎ木の実験 | 40 |
| 井上 健:前会長豊国秀夫氏(1932−1992) | 41 |
| 池田登志男:[夏季例会合宿調査報告] 千曲川流域〜甲武信岳一帯の植物観察会 | 43-44 |
| 植物ニュース 168-175:168シロヒキオコシ(横内文人),169ヒメヒマワリ(横内),170シナノナデシコ,ミヤマナデシコ(横内),171シロバナタツナミソウ(横内),172クロガラシ(横内), 173オオイタドリ(横内),174ナタネタビラコ(奥原弘人),175メルケンカルカヤ(奥原) | 39, 41, 42 |
1992年 No.25
| 伊那谷産サツキヒナノウスツボについて | 1-3 |
| 林 一六:ケニア半乾燥地域における植生回復実験 | 4-11 |
| 土田勝義・松田行雄・田中茂・大木正夫・岩波均・倉科佳代・永富直子:北海道中部低地(三笠市・美唄市)のミズナラ二次林の植生 | 12-21 |
| 松田行雄:湿原植生の群落学的研究 Ⅵ −天狗原の12年間の動態− | 22-26 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記(7) | 27-28 |
| 池田登志男:佐久の植物分布図 (2) | 29-37 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 12 | 38-41 |
| 奥原弘人:下伊那の植物に思う | 42-43 |
| 池田登志男:[冬季例会合宿調査報告] 望月少年自然の家付近の植物(冬の木の芽)観察会 | 44 |
| 植物ニュース 160-167:160ツチアケビ(池田登志男),161ウスユキマンネングサ(横内文人),162オキジムシロ(横内),163コウリンタンポポ(横内),164コゴメバオトギリ(横内)165シロバナヒレハリソウ(横内),166セイヨウオオバコ(横内),167オオキンケイギク(横内) | 21. 43 |
1991年 No.24
| 林 一六:アカマツ林内のミズナラ幼樹の成長 | 1-4 |
| 橋渡勝也・門田裕一:北アルプス常念山脈とその山麓一帯のトリカブト類 | 5-9 |
| 井上 健:カタクリ,タデスミレ,トガクシソウの集団のサイズ構造 | 10-14 |
| 浅野一男:ベニバナヤマイワカガミの分類学的考察 | 15-19 |
| 馬場多久男:長野県に自生するカエデ科の検索表 | 17-19 |
| 奥原弘人:白馬村の特殊植物 | 20-21 |
| 池田登志男:佐久のヤドリギ(科)の分布 | 22-26 |
| 豊国秀夫:国際蛇紋岩生態学会議に出席して | 26 |
| 池田登志男:佐久の植物分布図 (1) | 27-32 |
| 奥原弘人:新知見あれこれ (9) | 33-35 |
| 浅野一男:下伊那地方フロラ新知見 Ⅴ | 36-41 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記(6) | 42-43 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 11 | 44-63 |
| 北條慎一:暖温二帯植物いろいろ Ⅱ | 64 |
| 土田勝義:松本市の街路樹 | 65-74 |
| 名取 陽:西イリアン(インドネシア領ニューギニア)中央高地の植物 | 75-86 |
| 白井幸長:[夏季例会合宿調査報告] 白樺公園登山口・物見石山・美ヶ原高原の植物観察会 | 87 |
| 平林陸男:[秋季例会合宿調査報告] 釜無川上流の洞ヶ沢上部の植物観察会 | 88 |
| 植物ニュース 148〜159:148メリケンカルカヤ(奥原弘人),149チャルメルソウ(奥原),150ミヤマウコギ(奥原),151クロバナウマノミツバ(奥原),152ケヤキ(横内文人・横内正),153モウズイカ(横内),154キクタニギク(横内),155ホザキヤドリギ(横内),156シロバナムラサキウマゴヤシ(横内)157セイヨウオオバコ(横内),158シロバナガガイモ(横内),159カミコウチヤナギ(奥原) | 21, 35, 64 |
1990年 No.23
| 井上 健:ツキヌキソウ(スイカズラ科)の繁殖生物学 −予備的な報告− | 1-4 |
| 今井建樹:キバナアキギリの新変種 −キソキバナアキギリ(新称) | 5 |
| 栗田正秀:アマミセイシカの毛と葉の維管束 | 6-8 |
| 原 忠雄:山梨・長野両県にまたがる植物について | 9-10 |
| 浅野一男:下伊那地方フロラ新知見 Ⅳ | 11 |
| 奥原弘人:新知見あれこれ (8) | 12 |
| 池田登志男:長野県内のヒメウラジロの分布 | 13-14 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記(5) | 15-16 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 10 | 17-30 |
| 浅野一男:ヤマイワカガミの紅花品 | 31 |
| 豊国秀夫:塚田松雄先生の講演会について | 31 |
| 清水建美:分岐分類学と分断生物地理学 | 32-35 |
| 北條慎一:暖温二帯植物いろいろ | 36 |
| 奥原弘人:植物雑記 | 37 |
| 土田勝義・松田行雄・大木正夫:ゴルフ場開発と植物 −2事例からみた影響調査報告− | 38-47 |
| 豊国秀夫:花粉学入門 (2) | 48-50 |
| 山本雅道・豊国秀夫:長野県植物誌分布図作成システムについて | 51-52 |
| 白井幸長:[夏季例会合宿調査報告] 湯ノ丸高原・籠ノ登山・池ノ平・三方ヶ峰の植物観察会 | 53-54 |
| 赤羽敏明:[秋季例会合宿調査報告] 木曽南部の暖帯植物観察会 | 55-56 |
| 植物ニュース 140-147:140レンプクソウ(今井建樹),141ハルナユキザサ(池田登志男),142日本産ヒダカソウ属新亜種(豊国秀夫),143シロバナヒオウギアヤメ(横内文人),144エゾウコギ(吉沢健・池田登志男),145サカネラン(吉沢・池田),146キブシ(横内・横内正),147ホコガタアカザ(横内) | 5, 54, 56 |
1989年 No.22
| 井上 健:長野県のツレサギソウ植物 | 1-3 |
| 奥原弘人:新知見あれこれ (7) | 4 |
| 浅野一男:下伊那地方フロラ新知見 Ⅲ | 5-6 |
| 栗田正秀:ツツジ属数種の花式図 | 7-8 |
| 中山 冽:タコノアシPenthorum chinense の群落 | 9-10 |
| 船越眞樹:木崎湖におけるコカナダモの衰退 | 11-17 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 9 | 18-27 |
| 豊国秀夫:国際バイオシステマティックス・シンポジウム | 27 |
| 柴田 治:逆転樹木限界 | 28-30 |
| 清水建美:再び、インド植物紀行記 | 31-33 |
| 豊国秀夫:花粉学入門 (1) | 34-37 |
| 井上 健:ツレサギソウ属植物の系統と進化 | 38-40 |
| 伊藤文男:[特別寄稿] 天竜川流域における北限地域のカシ林 | 41 |
| 梶 幹男:亜高山帯針葉樹の生態地理学的研究−オオシラビソの分布パターンと温暖期気候の影響− | 42-46 |
| 馬場多久男:長野県の巨樹・巨木林調査について | 47 |
| 森泉恒男:[夏季例会合宿調査報告] 川上村・天狗山と南相木村・栗生川の植物採集 | 48 |
| 草間 勉:[秋季例会合宿調査報告] 仁科三湖から黒沼高原・大谷原への植物採集会 | 49・41 |
| 橋渡勝也:[秋季例会合宿調査報告] 木曽駒ヶ岳西方山麓の植物採集会 | 50-51 |
| 奥原弘人:杉本順一先生を悼む | 52 |
| 植物ニュース 132-139:132ヒメタケシマランの黄熟品(今井建樹),133ハルナユキザサ(池田登志男),134サツキヒナノウスツボ(浅野一男),135コマガタケシラベ(今井)136オオイタドリ(横内文人・横内正),137オオアブノメ(今井),138ネコヤマヒゴタイ(今井),139オウレンの花色(奥原弘人) | 30, 40, 51 |
1988年 No.21
| 吉玉国二郎・酒谷昌孝・赤塚陽一石倉成行:タデ科植物のアントシアン分布と化学分類学研究 | 1-7 |
| 栗田正秀:ツツジ属2種における冬芽の鱗片 | 8-11 |
| 清水建美:ニシキギ科植物の花序のつき方 | 12-13 |
| 今井建樹:チチブリンドウ | 14-15 |
| 奥原弘人:新知見あれこれ (6) | 16-17 |
| 池田登志男:佐久東部山地の植物分布 | 18-24 |
| 浅野一男:下伊那地方フロラ新知見 Ⅱ | 25-27 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記(4) | 28-30 |
| 横内 正・横内文人:中部信州ブナ林の植生(3)−南安曇郡南部− | 31-32 |
| 清水建美:インド・ヒマラヤ植物紀行 | 33-35 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 8 | 36-48 |
| 松浦 正:[特別寄稿] 免疫遺伝子の研究 | 49-50 |
| 北村文雄:[特別寄稿] 芝草の分類と生態 | 51-58 |
| 豊国秀夫:[講座] 植物学ラテン語初歩 (5) | 59-60 |
| 和田 清:植物に関する二,三 | 61 |
| 草間 勉:北安曇野の野生の桜について | 62 |
| 伊藤文男:[夏季例会合宿調査報告] 青木川上流域の植物採集会 | 63-64 |
| 森泉恒男:[秋季例会合宿調査報告] 馬坂・広河原・田口峠の植物採集 | 65 |
| 植物ニュース 113-131:113チャボガヤ(奥原弘人),114ヒメホテイラン(今井建樹),115サンプクリンドウ(今井),116キバナノマツバニンジン(今井),117ワタムキアザミ(元島清人),118カライトソウ(元島),119オオアワガエリ(奥原),120ベニバナイチヤクソウ(白花)(今井),121タカネアオチドリ(今井),122イヌヒメコヅチ(今井),123タケシマラン(奥原),124ケショウヤナギ(山﨑林治),125ツルガシワ(今井),126オオイタドリ(横内文人),127シロバナサワギキョウ(元島),128スギ(クマスギ)(元島),129ミドリワレモコウ(?),130シロバナミヤマモジヅリ(元島),131ヤエタカネセンブリ(元島) | 11, 13, 24, 27, 35, 48, 60, 64, 67 |
1987年 No.20
| 清水建美:長野県植物研究会の歩み | 1-2 |
| 白岩善博:植物とCO2 | 3-10 |
| 井上雅好:生物への新たなストレス-電場の影響− | 11-15 |
| 田中 修:開花時刻の調節 | 16-19 |
| 藤森 嶺:たばこの香気成分 | 20-23 |
| 鈴木和雄:ヒナウスツボ群(ゴマノハグサ科)の開花期における問題 | 24-25 |
| 大沢雅彦・滝口正三:植生帯の成立と分化 -日本のブナ林の生態地理学的考察 | 26-30 |
| 橘ヒサ子・笹原健二・次原 悟:風蓮湿原高層湿原部におけるミズゴケ類の生産について | 31-55 |
| 甲山隆司:北八ヶ岳の亜高山帯シラビソ・オオシラビソ・ダケカンバ混交林の動態 | 36-41 |
| 梶 幹男:カメルーン南西部熱帯多雨林の組成および構造 -Tetraberlinia bifoliolataの個体群構造からみた群落の動態 | 42-48 |
| 戸田善宏:スギ科樹木の核学的研究 | 49-54 |
| 若林三千男:雌雄異株のモミジチャルメルソウ | 55-57 |
| 加藤雅啓:根の起源と維管束植物の分類 | 58-61 |
| 戸部 博:キンポウゲ科の花の三数性 | 62-65 |
| 門田裕一:長野県のトリカブト類(キンポウゲ科)について | 66-72 |
| 酒井 昭:植物の寒冷気候に対する適応戦略 | 73-77 |
| 只木良也:物質生産における森林生態系の特徴 | 78-81 |
| 渡辺隆一:木本植物の開芽過程 | 82-86 |
| 横内 正・横内文人:中部信州ブナ林の植生 (2) -東筑摩郡南部・小県郡西部 | 87-89 |
| 和田 清・池田信三・横内 正:長野県北部の渓谷林 -ジュウモンジシダ-サワグルミ群集の位置づけ | 90-93 |
| 馬場多久男:伊那地方の天然生アカマツ林の種組成と地位指数の関係について | 94-99 |
| 橋渡勝也:長野県篠ノ井における市街地を中心としたタンポポ分布調査 | 100-103 |
| 栗田正秀:レンゲツツジの苗条の毛 | 104-105 |
| 浜 栄助:南西諸島[沖縄諸島(琉球列島)・薩摩諸島]のスミレ | 106-108 |
| 奥原弘人:新知見あれこれ (5) | 109-110 |
| 池田登志男:佐久東部山地植物分布ニュース | 111-112 |
| 浅野一男:下伊那地方フロラ新知見 Ⅰ | 113 |
| 土屋 守:日光産カラフトモメンヅルについて | 114-115 |
| 高橋秀男・横内文人:タチヒルガオが長野県に帰化する | 116-117 |
| 草間 博:佐久の帰化植物記録 | 118-121 |
| 大塚孝一:長野県におけるチャセンシダ属種間雑種の産地及びその識別について | 122-123 |
| 花里 弘:佐久東部山地の主なシダ植物 | 124 |
| 高橋秀男:遠山川支流北又沢におけるヤシャイノデの分布 | 125-128 |
| 落合照雄:長野県主要5河川の河床付着藻類と水質汚濁 | 129-134 |
| 和田 清:昭和61年度特定植物群落調査について | 135 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 7 | 136-146 |
| 清水建美:第2回国際生物学賞授賞式に列席して | 147-148 |
| 馬場多久男・渡辺隆一・土田勝義:創立20周年記念自然観察会の記録 | 149 |
| 亀山 章:長野県植物研究会創立20周年記念大会 | 150 |
| 池田登志男:[夏季例会合宿調査報告] 御座山の植物採集 | 151 |
| 楯 誠治:[秋季例会合宿報告] 南木曽岳のまわりの植物採集 | 152 |
| 植物ニュース 99-112:99キンモウワラビ(山崎惇),100ユキツバキ(和田清),101ウサギギクとチョウジギクの雑種(清水建美・原信彦),102シロバナナンテンハギ(横内文人),103ミズイロアオイ(新称)(横内),104シチゴサンアオイ(新称)(横内),105ミドリヨシノ(横内),106ハリエンジュ(ニセアカシア)(横内),107ウスギオウレン(清水),108ナガバノスミレサイシン(浅野一男),109オオイタドリ(横内),110ヤエノモモ(横内),111ミヤマキンバイ(豊国秀夫),112ムラサキシロウマリンドウ(豊国) | 30, 77, 113, 115, 121, 128, 134 |
| 植物ニュース索引:1〜112 | 158-159 |
| 著者名索引(アルファベット順):研究会誌第1号~第20号 | 160-165 |
1986年 No.19
| 栗田正秀:エゾムラサキツツジの盾形毛 | 1-2 |
| 豊国秀夫:興味あるタイ国産リンドウ属植物 | 3 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記 (3) | 4-5 |
| 浅野一男:下伊那地方のフロラに追加されるべき植物2種 | 6 |
| 横内 正・横内文人:中部信州ブナ林の植生 (1) 東筑摩郡北部 | 7-9 |
| 吉田直隆:高山風衝地の植物群落をとりまく温度的環境-木曽駒ケ岳における地温観測の結果から- | 10-13 |
| 清水建美:沙漠と氷河 -中国の旅− | 14-19 |
| 中山 冽:中国で垣間見た植物 | 20-23 |
| 土田勝義:ブータンの植物調査 | 24-26 |
| 和田 清:特定植物群落の選定調査について | 27-28 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 6 | 29-36 |
| 沖津 進:[特別寄稿] ハイマツ帯の動態 -ハイマツ群落の動態とハイマツ帯の消長 | 37-42 |
| 豊国秀夫:[講座] 植物学ラテン語初歩 (4) | 43-44 |
| 横内文人:[長野県植物誌 資料Ⅹ] 「野草」に掲載されたフロラ関係文献目録(1) | 45-49 |
| 渡辺隆一:植物季節と自然教育 | 50 |
| 吉江清朗:1株のイヌブナ | 51 |
| 楯 誠治:春山林道の植物採集 | 52 |
| 池田登志男:茂木山の植物採集 | 53 |
| 植物ニュース 83-98:83グンバイズル(横内文人),84オオイタドリ(浅野一男)・(横内),85ケナシアオギリ(横内),86ミヤマママコナ(横内),87シロバナホトケノザ(横内),88アコウグンバイ(イヌグンバイナズナ)(横内),90オオモミジ(清水建美),91ヤシャゼンマイ(中山洌),92ハイハマボッス(和田清),93タカネソヨゴ(横内),94アカエゾマツとエゾマツ(清水建美),95ウワウルシ(清水),96ハナノキ(清水),97イロハカエデ(清水),98ヤエザキバイカオウレン(奥原弘人) | 2, 6, 23, 26, 49, 52,53 |
1985年 No.18
| 栗田正秀:ヤマツツジの多細胞普通毛 | 1-2 |
| 奥原弘人:新知見あれこれ(4) | 3 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記(2) | 4-5 |
| 堤 久:長野県のシダ採集ノート 2 | 6-9 |
| 土田勝義:高山帯の植生回復に関する研究 2 現地における移植実験 | 10-15 |
| 鈴木由告・清水長正・秋山好則:吾妻山系西大嶺の亜高山帯上部における岩塊斜面と森林の群落構成からみた過去の森林限界 | 16-22 |
| 齋藤信夫:青森県の高茎草本群落 | 23-25 |
| 浅川富雄:長野県に急繁殖したイヌキクイモ | 26-30 |
| 名取 陽:東アフリカ,エルゴン山とキリマンジャロ山の植物 | 31-40 |
| 清水建美:ニュージーランドの高山植物と植生 | 41-46 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 5 | 47-54 |
| 豊国秀夫:[講座] 植物学ラテン語初歩 (3) | 55-56 |
| 岩田好宏:生物教育の現状と将来 | 57-59 |
| 横内文人:[長野県植物誌] 「植物採集ニュース」に掲載されたフロラ関係文献目録 | 60-62 |
| 下野園 正:[夏季例会合宿調査報告] 田立森林公園の植物採集 | 63 |
| 渡辺隆一:[秋季例会合宿調査報告] 野々海池周辺の植物採集 | 63-64 |
| 伊藤文男:[秋季例会合宿調査報告] 天竜川流域の植物採集 | 64-65 |
| 俣野敏子:佐野 泰先生を悼む | 65 |
| 植物ニュース 76-82:76シラカンバ(奥原弘人),77クロユリ(清水建美),78シロタエヒマワリ(浅川富雄),79コシカギク(オロシャギク)(浅川),80ヒメカイウ(和田清),81イワガネソウとイワガネゼンマイ(奥原),82ニセシラゲガヤ(新称)(清水) | 2, 22, 30, 40, 56 |
1984年 No.17
| 松田行雄・土田勝義:美ヶ原焼山のブナ林の群落学的研究 | 1-7 |
| 小泉武栄:北アルプス白馬・鹿島槍連峰の強風地における植生観察 | 8-11 |
| 浅川富雄:北海道の帰化植物 -長野県との現況比較- | 12-18 |
| 清水建美:ツリフネソウ属の染色体数 | 19-25 |
| 豊国秀夫:ハルリンドウとその近縁種 | 26-28 |
| 奥原弘人:新知見あれこれ(3) | 29-30 |
| 望月精一:上小地方に初記録のシダ3種 | 31 |
| 大塚孝一:長野県のシダ植物雑記(1) | 32-33 |
| 相馬潔・斉藤紀:ワラジムシの糞の分解 | 34-37 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 4 | 38-47 |
| 丸山利雄:長野県植物研究者伝 9 横内 斎 抄伝 | 48-49 |
| 豊国秀夫:リンネ植物園 | 50-55 |
| 清水建美:[長野県植物誌 資料 Ⅷ] 松本市フロラ作成のためのチェックリスト | 56-76 |
| 渡辺隆一:[夏季例会合宿調査報告] 雨飾山麓の植物採集 | 77 |
| 馬場多久男:[秋季例会合宿調査報告] 信州大学農学部西駒演習林の植物採集 | 77-78 |
| 下野園 正:[秋季例会合宿調査報告] 小路峠・柿其渓谷の植物採集 | 78-79 |
| 豊国秀夫:前川先生を偲んで | 80 |
| 奥原弘人:前川先生の思い出 | 81-82 |
| 植物ニュース 72-75:72チシマウスバスミレ(藤沢正平・柳荘一郎),73シロバナアブラギク(望月精一),74フキ(清水建美),75ヤナギ類Salix spp(奥原弘人) | 30, 31, 33, 88 |
1983年 No.16
| 金井弘夫:長野県フロラ作成資料の電算機処理 | 1-7 |
| 豊国秀夫:センブリ類の分類体系 | 8-10 |
| 奥原弘人:新知見あれこれ(2) | 10-12 |
| 大塚孝一:信州の羊歯植物研究 V | 13-17 |
| 渡辺隆一:カヤノ平地域におけるブナ林について | 18-22 |
| 山崎 惇:東日本ブナクラス域におけるコナラ林の概観(Ⅳ) | 23-24 |
| 土田勝義:高山帯の植生回復に関する研究 1.現地における播種実験 | 25-30 |
| 浅川富雄:長野県の帰化植物の動態(3) | 31-37 |
| 落合照雄:千鹿頭池の植物プランクトン | 38-41 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 3 | 42-49 |
| 丸山利雄:長野県植物研究者伝 8 小泉秀雄抄伝 | 50-52 |
| 小泉武栄:[特別寄稿] 世界的視野からみた日本の高山帯 | 53-57 |
| 清水建美:[長野県植物誌資料 Ⅵ] マンテマ属の種類と分類 -長野県フロラ作成のために− | 58-61 |
| 横内文人:[長野県植物誌 資料Ⅶ]「長野県史蹟名勝天然記念物調査報告」に掲載されたフロラ関係文献目録(2) | 62-65 |
| 和田 清:[夏季例会合宿調査報告] カヤノ平の植物採集 | 66 |
| 名取 陽:[夏季例会合宿調査報告] 横川峡・経ヶ岳の植物採集 | 66-67 |
| 八幡泰平:[秋季例会合宿調査報告] 八坂村・野平の植物採集 | 67 |
| 清水建美:長野県植物誌のためのデータ入力 | 72 |
| 植物ニュース 64-71:64タニウツギとニシキウツギ(堀金富平),65チシマゼキショウ(清水建美),66カワラアカザ(浅川富雄),67ヤマコウバシ(和田清),68キヌガサソウ(清水),69ミズハコベ(豊国秀夫),70クロユリ(清水),71アカザ(浅川) | 22, 24, 37, 52, 61, 65 |
1982年 No.15
| 奥原弘人・松田行雄:サクラ属の新雑種 | 1-3 |
| 清水建美:高山植物の覚え書 II | 4-5 |
| 清水建美・岡崎純子:トガクシタンポポについて | 5-6 |
| 奥原弘人:新知見あれこれ | 7-9 |
| 山崎 惇・高橋秀男:タルマイスゲの新産地 | 10-11 |
| 大塚孝一:長野県産羊歯植物目録 | 12-18 |
| 大塚孝一:信州の羊歯植物研究 IV | 19-22 |
| 堤 久:長野県のシダ採集ノート | 23-24 |
| 山崎 惇:東日本ブナクラス域におけるコナラ林の概観(Ⅲ) | 25-26 |
| 松田行雄:湿原植生の群落学的研究 V. 居谷里湿原の植生 | 27-33 |
| 齋藤信夫:青森県のカラスザンショウ林 | 34-37 |
| 浅川富雄:松本安曇平の植物気候 特に松本市周辺の特殊気候に注目して | 37-42 |
| 落合照雄:天竜川の底生藻類と水質汚濁(1) | 43-47 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物名方言 2 | 48-53 |
| 丸山利雄:長野県植物研究者伝7 田中貢一抄伝 | 54-55 |
| 正宗厳敬:牧野富太郎先生を偲びて | 55-56 |
| 三浦宏一郎:(特別寄稿) 菌類のはなし | 57-62 |
| 横内文人:[長野県植物誌 資料Ⅴ] 「長野県史蹟名勝天然記念物調査報告」に掲載されたフロラ 関係文献目録(1) | 63-68 |
| 名取 陽:八ヶ岳・阿弥陀岳広河原沢の植物採集 | 69 |
| 八幡泰平:岩岳・親ノ原の植物採集 | 70 |
| 和田 清:黒姫山北麓の植物採集 | 70 |
| 豊国秀夫:[講座] 植物学ラテン語初歩(2) | 71-75 |
| 植物ニュース54-63:54シロオオバコ(横内文人),55マルバノキ(堤久),56ハクウンラン(土屋守),57フナコシイノデ(堤久),58コシノカンアオイ(藤沢正平),59ナンテンハギ(土屋),60ブタナ(藤沢),61ノゲイヌムギ(浅川富雄),62アレチノチャヒキ(浅川),63ツルマンネングサ(浅川) | 3, 18, 26 |
1981年 No.14
| 横内文人:長野県産ツツジ属の一同定法 | 1-4 |
| 豊国秀夫:リンドウ類の分類体系 | 4-7 |
| 清水建美:高山植物の覚え書 I | 8-9 |
| 大塚孝一:信州の羊歯植物研究 III | 10-15 |
| 山崎 惇:東日本ブナクラス域におけるコナラ林の概観(Ⅱ) | 16-17 |
| 和田 清:西ドイツ中部のブナ林域 | 18-22 |
| 渡辺隆一:植物の季節はいかにしてきまるか | 23-31 |
| 相馬 潔:落葉の分解と土壌生物 | 32-35 |
| 浅川富雄:野外植物の生育状態と気候 | 36-38 |
| 吉玉国二郎:花の色について | 39-41 |
| 清水建美:オレゴンの旅 | 42-44 |
| 浅野一男:長野県下伊那地方の植物方言 | 45-52 |
| 丸山利雄:長野県植物研究者伝6. 小山海太郎抄伝 | 53-54 |
| 苅住 昇:植生と根系に関する研究 | 55-61 |
| 山崎 惇:佐久市兜山の植物採集 | 62 |
| 大木正夫:風吹山の植物採集 | 63 |
| 清沢晴親:横内斎さんを想う | 63-66 |
| 豊国秀夫:[講座] 植物学ラテン語初歩(1) | 67-71 |
| 植物ニュース42-53:42ネビキミヤコグサ(浅川富雄),43カラメドハギ(浅川),44ヒダアザミ(奥原弘人),45キセルアザミ(奥原),46ミツバツツジ類(奥原),47セイタカアワダチソウ(浅川),48ビロードモウズイカ(浅川),49シダレスギ(横内文人),50アオザゼンソウ(松田行雄・横内文人),51クリンソウ(奥原),52フクジュソウ(松田・横内),53クサノオウ(川窪伸光) | 17, 22, 31, 35, 38, 41, 77 |
1980年 No.13
| 能代克巳:果樹における穂植物と台植物の相互関係 | 1-4 |
| 若原正博:美ヶ原周辺のすみれについて | 5-6 |
| 清水建美:植物地理学寸評 | 7-9 |
| 横内 斎:長野県に新たに加わる植物 VII | 10 |
| 山崎 惇:東日本ブナクラス域におけるコナラ林の概観 (Ⅰ) | 11-13 |
| 浅川富雄:長野県の帰化植物の動態(2)-中信を主に盛衰のあとを追う− | 14-19 |
| 落合照雄:松本市内河川の水質と底生藻類 | 20-25 |
| 柳沢新一:コケの共存バランス, 追加分・藻類(らん藻)考 | 26-36 |
| 浅野一男:長野県下伊那郡阿南町新野の植物名方言 | 37-46 |
| 丸山利雄:長野県植物研究者伝5 白沢保美 抄伝 | 47-48 |
| 横内 斎・横内文人:長野県植物誌資料 III 「長野林友」に掲載されたフロラ関係文献目録 | 49-53 |
| 横内文人・楯 誠治:長野県植物誌資料 Ⅳ 「信濃教育」に掲載されたフロラ関係文献目録(2) | 53-54 |
| 伊藤文男:[夏季例会合宿調査報告] 豊口山の植物採集 | 55 |
| 渡辺隆一:[秋季例会合宿調査報告] 志賀高原・地獄谷の植物採集 | 56 |
| 植物ニュース35-41:35フジアザミ(奥原弘人),36フタツキジノオ(奥原),37ミツバツツジ類(金井弘夫),38エンビセンノウ(望月精一),39ツガザクラ(奥原),40シライトソウとナツエビネ(奥原),41シャジクソウ(松田行雄・横内文人) | 6, 13 |
1979年 No.12
| 中山包:ヘテロスタイリー(異花柱性)とその周辺 | 1-5 |
| 奥原弘人:木曽谷産植物目録補遺 | 5 |
| 豊国秀夫:北海道の高山植物 | 6-11 |
| 横内斎:信州植物の地史的分布 | 12-13 |
| 横内斎:長野県に新たに加わる植物 Ⅵ | 13 |
| 浅野一男:東海地方東部のモミ林の構造と分布,その2 | 14-26 |
| 岡部牧夫:法面草として有望な志賀高原のキク科植物 | 27-28 |
| 浅川富雄:路辺植物の耐寒性を比較する | 29-33 |
| 高橋秀男:長野県のアメリカネナシカズラ | 34 |
| 川崎圭造・浅田節夫:カラマツの立地と分布に関する諸問題 | 35-38 |
| 落合照雄:天龍川へ注ぐ三枝流河川の底生藻類と水質汚濁 | 39-42 |
| 柳沢新一:コケの共存バランス補遺,生理・病理・生態学的考察 | 43-49 |
| 清水建美・金井弘夫:「長野県植物誌」作成の方法 | 50-54 |
| 丸山利雄:長野県植物研究者伝4.矢沢米三郎抄伝 | 55-56 |
| 桃谷好英(話題提供)・清水建美(抄録):[シンポジウム]−現代の成分分類学 | 57-58 |
| 清水建美:長野県植物誌資料Ⅰ 「信濃博物学雑誌」に掲載されたフロラ関係文献目録 | 59-63 |
| 清水建美・木下栄一郎:長野県植物誌資料Ⅱ 「信濃教育」掲載されたフロラ関係文献目録 | 64-65 |
| 林一六:独鈷山採集会報告 | 66 |
| 伊藤静夫:一夜山の植物採集 | 67 |
| 植物ニュース29〜34:29オオシダザサ(今井健樹),30ハナヒョウタンボク(今井),31ヒメカンアオイ(今井),32マムシグサ(木下栄一郎・清水建美),33タルホコムギ(高橋秀男・橋渡勝也),34モノドラカンアオイ(若原義文) | 5, 33, 34, 65, 66 |
1978年 No.11
| 浅野一男:東海地方東部のモミ林の構造と分布,その1 | 1-24 |
| 浅野一男・中山 洌:スダジイ群団領域の非帯状植物社会,シバヤナギ群集(新) | 25-31 |
| 浅川富雄:松本・名古屋両市街地の人里植物を対比する−特に帰化植物の動きを追って | 32-41 |
| 馬場多久男:枝状の形態からみた落葉広葉樹の分類(1) | 42-53 |
| 横内 斎:長野県に新たに加わる植物 V | 53 |
| 木下栄一郎・清水建美:長野県堀金村におけるマムシグサ集団の一観察 | 54-56 |
| 奥原弘人:賎母国有林の植物 | 57-66 |
| 中本信忠・長島英二:菅平ダム湖における珪藻の同調成長現象について(予報) | 67-70 |
| 柳沢新一:コケの共存バランス | 71-75 |
| 丸山利雄:長野県植物研究者伝 3 河野冷蔵抄伝 | 76-77 |
| 清水建美:[シンポジウム] 裸茎類−原始陸上植物(西田誠氏講演の抄録) | 78-82 |
| 中山 冽:[夏季例会合宿報告] 男山の植物を訪ねて | 82-83 |
| 伊藤静夫:[秋季合宿調査報告] 小菅神社のキタゴヨウ林 | 83-84 |
| 浅野一男:鈴木時夫先生の御逝去を悼む | 85-86 |
| 大木正夫:鈴木時夫先生の思い出 | 86 |
| 植物ニュース18〜28:18ヒカゲツツジ(和田清),19タカオワニグチソウ(今井健樹),20エゾナミキソウ(オオナミキソウ)(今井),21キヌガサソウ(アラゲハンゴンソウ)(横内文人),22カミコウチアザミ(新称)(奥原弘人),23トゲジシャ(浅川富雄),24トラキチラン(楯誠治),25ゴウシュウアリタソウ(浅川),26キバナタカサブロウ(浅川),27メマツヨイグサ(浅川),28ヒメニラ(清水建美) | 53,56,66,77,84 |
1977年 No.10
| 原 寛:長野県植物研究会10周年に寄せて | 1-2 |
| 大井次三郎:しかくだけ(しほうちく) | 2-3 |
| 北川政夫:日本産植物数種の学名考証 | 3-4 |
| 鈴木貞雄:長野県から報告されたササ類 | 4-9 |
| 高木典雄:日本北端石灰岩地の蘚類フロラ | 9-11 |
| 前田禎三:富士山のカラマツ天然林 | 12-20 |
| 石川慎吾・内藤俊彦・飯泉茂:荒雄川のミチノクシロヤナギ林の発達に関する2,3の知見 | 20-30 |
| 鈴木兵二:霧ヶ峰湿原植生の今昔 | 30-35 |
| 沼田 真:ドナウ盆地の植生,その他 | 36-42 |
| 木村陽二郎:徳川時代渡来の植物図譜 | 43-51 |
| 本田正次:長野県の天然記念物と私−その植物について− | 51-53 |
| 倉田 悟:信州下伊那郡大鹿村の植物方言 | 54-58 |
| 正宗巌敬:植物学者の見た屋久島の今昔 | 59-64 |
| 室月欣二:長野県と陸水生物学 | 64-65 |
| 四手井綱英:黒四ダムサイトの修景について | 66-71 |
| 前川文夫:古赤道分布とカンアオイ類 | 72-74 |
| 鈴木時夫:群集これから−群集の本体はなんであろうか− | 75-80 |
| 浅野一男:チマキザサ−ショウジョウスゲ群集について | 80-90 |
| 和田 清:長野県における山地帯以下の森林植生−いわゆる中間温帯について− | 90-97 |
| 林一六・浅野一男・土田勝義・和田清:長野県の社寺林(予報) | 97-101 |
| 土田勝義:美ヶ原高原の緑化実験 | 101-111 |
| 大木正夫:森林のとりあつかい | 111-114 |
| 佐野 泰・氏原暉男・俣野敏子:環境の変化とハイマツの生長 | 114-117 |
| 入来義彦:植物分類学の一考察−鞭毛藻類とキンポウゲ科植物を中心として | 117-118 |
| 清水建美:高等植物の微細構造と分類−特にホウセンカ属植物を中心として− | 118-124 |
| 久保田秀夫:八ヶ岳山麓のサクラ−マメザクラとタカネザクラの雑種− | 124-127 |
| 横内 斎:長野県に新たに加わる植物 Ⅳ | 128 |
| 橋渡勝也・高橋秀男:木曽郡南木曽町柿其で発見した長野県新産植物2種 | 128-129 |
| 清水建美:欧州でみた日本植物研究史Ⅱ | 130-137 |
| 丸山利雄:長野県植物研究者伝2.斎田功太郎抄伝 | 137-138 |
| 松田行雄:長野県植物研究会創立10周年記念大会 | 139 |
| 植物ニュース11〜17:11オオヒメワラビモドキ(奥原弘人),12ヒナチドリ(奥原),13マルバウマノスズクサ(奥原),14ツゲ(奥原),15ノリクラアザミ(奥原),16キバナイカリソウ(清水建美),17シロバナタンポポ(清水) | 71,129 |
1976年 No.9
| 鈴木時夫:群集事なかば | 1-8 |
| 岡部牧夫:奥志賀林道の法面植生について | 9-17 |
| 水野瑞夫・田中俊弘・福原裕子・甲谷俊彦・大内幸雄・岡田裕:岐阜県のアカマツ林について | 18-26 |
| 荒川袈裟利:トガクシソウの生態と繁殖環境について | 27-36 |
| 丸山利雄:深雪地飯山の常緑低木 | 37 |
| 浅川富雄:長野県の帰化植物の動態(1) | 38-44 |
| 大塚孝一:信州の羊歯植物研究 II | 45-53 |
| 横内 斎:長野県に新たに加わる植物 III | 54 |
| 清水建美:欧州でみた日本植物研究史 I | 55-63 |
| 丸山利雄:長野県植物研究者伝 Ⅰ 田中芳男抄伝 | 63-65 |
| 清水建美:[シンポジウム] 植物地理学からみた日本フロラの特性(村田源氏講演の抄録) | 66-72 |
| 今井建樹:[夏季例会採集会報告] 釜無渓谷の植物 | 72-73 |
| 和田 清:[秋季合宿調査報告] 米子谷の植物を追って | 73-74 |
| 柳沢新一:蚕景山附近の植物と呼び名、補遺 | 75 |
| 植物ニュース1-10:1ハコネシダ(奥原弘人)、2エビラシダ(奥原)、3オオバノハチジョウシダ(奥原)、4ギンバイソウ(奥原)、5クロビイタヤ(奥原)、6ツリシュスラン(横内斎)、7ミタケノイバラ(横内)、8ハルザキヤマガラシ(浅川富雄)、9セイヨウノコギリソウ(浅川)、10ケショウヤナギ(清水建美) | 8, 26, 44, 74 |
1975年 No.8
| 鈴木時夫:群集事始め | 1-10 |
| 原 嘉彦:Fiddle Headと葉軸・羽軸の溝の形成並びに展開過程の研究 −イヌワラビとミヤマシケシダの比較研究をとおして− | 11-17 |
| 大塚孝一:信州の羊歯植物研究 Ⅰ | 18-28 |
| 横内 斎:長野県に新たに加わる植物 Ⅱ | 29-30 |
| 横内文人:梓川下流におけるケショウヤナギ゙ 第1報 分布 | 30-35 |
| 奥原弘人:「木曽谷の植物」補正 | 36 |
| 浅川富雄:長野県における裸地再生群落の構成種とその立地別消長 | 37-45 |
| 伊藤文男:下伊那の帰化植物 | 46-51 |
| 土田勝義・加藤久雄・中谷易功・山口詳二朗:霧ヶ峰高原におけるヒメジョオン類の生態(1) | 52-66 |
| 水野瑞夫・田中俊弘・福原裕子・甲谷俊彦:奥美濃のブナ林について | 67-76 |
| 和田 清:長野盆地周辺の植生とその保護・保全 | 77-88 |
| 松田行雄:湿原植生の群落学的研究 III. 北アルプスの湿原植生 | 89-100 |
| 大木正夫:信州の土壌と植生 | 101-107 |
| 奥原弘人:[シンポジウム] 長野県南部と岐阜県東部のフロラの比較(井波一雄氏講演の要約) | 108-110 |
| 奥原弘人・松田行雄:[秋季合宿調査報告] 釜無渓谷の植物 | 111-112 |
| 柳沢新一:蚕景山付近の植物と呼び名 | 113 |
1974年 No.7
| 氏家暉男・俣野敏子:ソバ゙の生態型分化について | 1-7 |
| 横内 斎:長野県に新たに加わる植物 | 8-9 |
| 奥原弘人:イヌコリヤナギの枝垂 | 9 |
| 松田行雄:長野県産ミズゴケ類(Sphagnales)の分布並びに分類Ⅱ | 16-42 |
| 浅川富雄:亜高山帯の破壊に伴う人里植物の上昇 | 43-53 |
| 浅野一男:植物社会成立の地史的背景(3) | 54-56 |
| 土田勝義・三木 昇:乗鞍岳の森林植生の組成と構造 | 57-79 |
| 村上宣雄:希望が丘(滋賀県)におけるアカマツ林の植物社会学的研究 | 79-86 |
| 北川尚史:(特別寄稿)ナンジャモンジャゴケとコケの系統について | 87-91 |
| 伊藤静夫:夏季合宿報告:角間渓谷の植物 | 92-93 |
1973年 No.6
| 浅田節夫:ニホンカラマツの天然分布地域について | 1-11 |
| 坂本圭司:北八ヶ岳における縞枯れについて | 11-17 |
| 浅野一男:植物社会成立の地史的背景(2) | 17-27 |
| 神山隆之・浜 栄助:薩摩に見出された珍奇なスミレの雑種 | 27-29 |
| 浅川富雄:中部信州帰化植物 | 30-43 |
| 横内 斎:北安曇郡神城地区の植物 親海湿原を中心に | 44-46 |
| 志村義雄:長野県下における興味あるシダ植物(その1) | 47-53 |
| 松田行雄:長野県産ミズゴケ類(Sphagnales)の分布並びに分類 Ⅰ | 53-75 |
| 広瀬忠樹:(綜説)植物群落の物質生産 | 75-88 |
| 清水建美:[シンポジウム] 土壌と植生をめぐって(薄井宏氏の講演の要約・解説) | 89-95 |
| 松田行雄:鉢盛山(黒川)採集会 | 95-97 |
1972年 No.5
| 中山 包:野草と雑草の種子の耐乾・耐湿性が植生上にもつ生態学的意義 | 1-9 |
| 荒川袈裟利:新しいシャクナゲの雑種”クロヒメシャクナゲ”について | 9-14 |
| 浜 栄助:ナンザンスミレについての考察 ”対馬にナンザンスミレをみて” | 15-19 |
| 浅川富雄:帰化植物の調査から霧ケ峰の現状を訴える | 19-26 |
| 浅野一男:植物社会成立の地史的背景(1) | 26-37 |
| 土田勝義:美ヶ原高原のコメツガ・シラビソ林の植生 | 37-45 |
| 北村智恵:亜高山帯針葉樹林下における倒木上着生植物群落(Ⅱ)-北八ヶ岳,木曽御岳における倒木上着生植物群落の構造と遷移- | 46-53 |
| 伊藤静夫:長野県のオオシラビソ-シラビソ群集について | 53-59 |
| 堀米和雄:ミヤマニガウリの花器保護の現象について | 59-64 |
| 小野貞雄:長野県における着色雪について(2) | 64-72 |
| 清水建美:[シンポジウム] 中部地方における植物分布の問題点(里見信生氏講演の要約) | 73-76 |
| 林 一六:ブラジル東部植物紀行 | 77-83 |
1971年 No.4
| 清水建美:日本産アザミ属植物の分類と新種ヤチアザミについて | 1-8 |
| 小林圭介:台湾の針葉樹林について | 8-17 |
| 和田 清:長野県内の植生図 | 17-21 |
| 浅川富雄:松本盆地にシラゲガヤの大繁殖 | 21-26 |
| 原 嘉彦:シダ植物の鱗片の研究(1) | 26-29 |
| 小野貞雄:長野県における着色雪について(1) | 29-40 |
| 山崎林治:庶民の森 | 41-42 |
| 土田勝義:自然保護運動集会に参加して | 42-47 |
1970年 No.3
| 浜 栄助:下伊那のスミレ | 1-12 |
| 横内文人:木曽谷のヒノキ林植生 | 12-18 |
| 八幡泰平:長野県のハイマツ群落 | 19-25 |
| 土田勝義:美ヶ原高原の植物生態学的自然保護の研究(1) | 26-31 |
| 林 一六:植物の生育型について(2) | 32-37 |
| 寺島虎男:雨飾山の植物の記録 | 38-41 |
| 中山 冽:黒倉山の調査報告 | 41-52 |
| 清水建美:[シンポジウム] ササ属植物の分類・地理・生態 (鈴木貞雄氏講演の要約) | 52-57 |
| 和田善三:アメリカの旅とリンドウ研究 | 57-61 |
| 清沢晴親:寺島虎男先生を悼む | 62 |
1969年 No.2
| 平林国男・高橋秀男:ハナカエデの生態学的研究(I)-自生地における植物相と植生- | 1-16 |
| 寺島虎男:安曇野の植物分布についての考察 | 17-24 |
| 名取 陽:標高と植物 | 24-30 |
| 松田行雄:長野県におけるミズゴケ類の分布並びに生態学的研究 | 31-43 |
| 伊藤静夫:長野市周辺におけるアカマツ林の植物社会学的研究 第一報 浅川三登山について | 44-48 |
| 林 一六:植物の生育型について(1) | 49-53 |
| 和田善三:リンドウ科植物の細胞学的研究、そのI | 54-58 |
| 清水建美:[シンポジウム] 植物社会学の基礎 (宮脇昭の講演の要約) | 59-62 |
| 奥原弘人:阿寺渓谷採集会 | 62-64 |
1968年 No.1
| 清水建美:高等植物における裏日本海要素について | 1-5 |
| 浅野一男:アカマツ林の植物社会学的研究−特に伊那谷を中心として− | 6-13 |
| 中山 冽:黒姫山の植物社会 | 14-23 |
| 林 一六:植物の生活様式の適応 | 24 |
| 横内 斎:菅平高原の植物 | 24-28 |
| 奥原弘人:木曽谷で問題になる二,三の植物 | 28-30 |
| 山崎林治:信州の植物研究家 | 31-36 |
| 清沢晴親:北アルプス餓鬼岳合宿調査報告 | 39-48 |